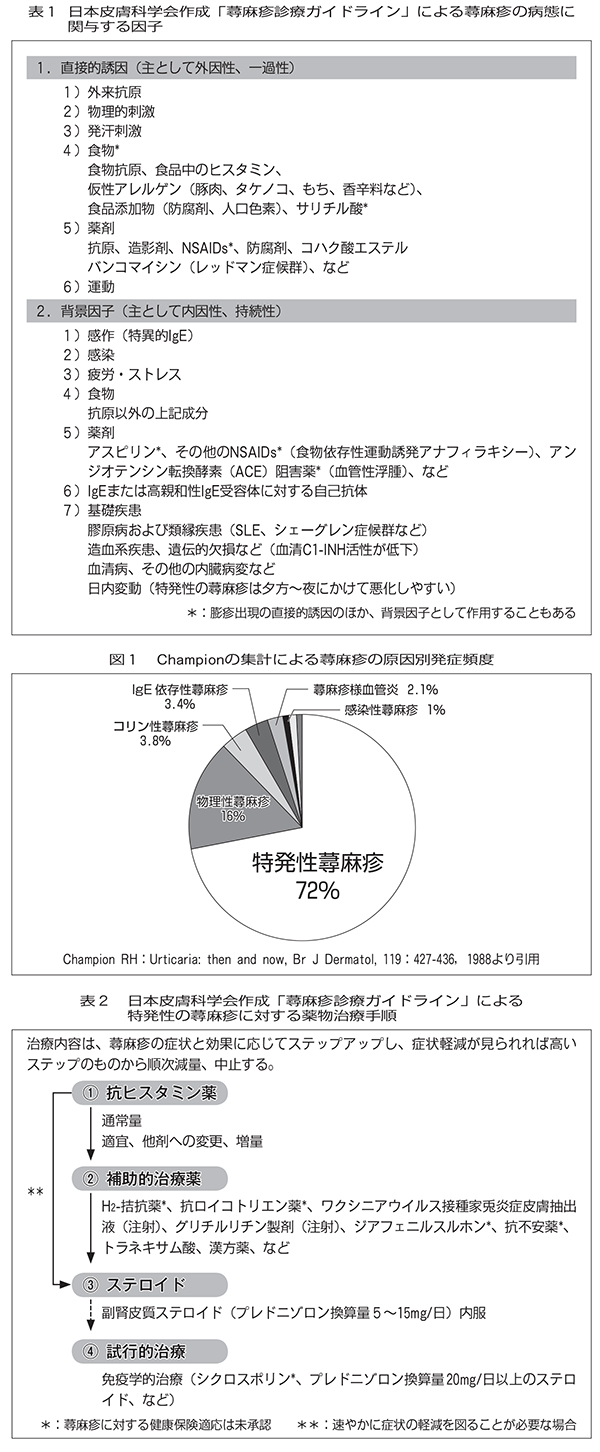医科2015.03.14 講演
[保険診療のてびき] 蕁麻疹の発症因子と治療方法
西宮市・はらだ皮膚科クリニック 原田 晋先生講演
1.蕁麻疹とは?
痒みと共に、限局性の発赤を伴った浮腫性変化を突然生じる皮膚疾患をいう。その本態は、真皮における血管の浮腫性変化であるため、個々の皮疹は数時間後にはあとかたを残さずに消褪することを特徴とする。ただし、経時的に場所を移動しつつ症状が持続する場合もある。そのため、蕁麻疹か否か診断に悩む際に筆者は、皮疹の数カ所にボールペンでマーキングをしておき、その箇所を患者本人または家族に帰宅後および翌日に観察してもらうとの方法を推奨している。その結果、マーキング部が跡形なく消褪していれば蕁麻疹と診断しうる。また、蕁麻疹の特殊型として、血管性浮腫またはクインケ浮腫との病態が存在している。これは、通常の蕁麻疹と比べて、より深い真皮下層ないし皮下組織における血管浮腫により生じる皮膚変化をいい、顔面特に眼瞼・口唇に好発する。一般的に個疹は通常の蕁麻疹とは異なり2〜3日持続し、かつ痒みを伴わない場合が多い。
2.蕁麻疹の臨床経過
蕁麻疹は通常、ある日突然に発症するが、その後の経過は二極化する傾向にある。すなわち、蕁麻疹全体の8割〜9割は1週間〜10日程度の経過で自然治癒し、急性蕁麻疹と称される。一過性のウイルス感染や、たまたま食べた食物が原因の場合などは、急性蕁麻疹の経過をとる。一方、蕁麻疹全体の1割〜2割は4週間以上蕁麻疹の出現が持続し、このような場合を慢性蕁麻疹と呼ぶ。なぜ4週間が慢性蕁麻疹の区切りかの理由として、Greavesらは、発症後1カ月以上続いている蕁麻疹患者の調査を行い、その結果約40%はその後1年以上にわたって膨疹の出没が持続していることを確認している。従って、4週間以上膨疹が持続した場合には、よほど積極的に原因解明や治療を行わないと、その後年余にわたり膨疹の出現が持続するリスクが高いということになる。
3.蕁麻疹の原因
日本皮膚科学会作成「蕁麻疹診療ガイドライン」による蕁麻疹の病態に関与する因子として、表1のような直接的誘因および背景因子が挙げられている。一般的に蕁麻疹はアレルギーの機序により発症するとのイメージが強いが、Championは1988年に2310例もの多数の蕁麻疹症例に関する大規模な集計を施行した。その結果、アレルギー的な機序の関与が疑われた蕁麻疹は、図1に示すごとく全体のうちのわずか3.4%にすぎなかった。従って現実的には、全蕁麻疹のうちでアレルギー性の機序で生じるものはごく一部であり、真皮内に存在しているマスト細胞からヒスタミンをはじめとする化学伝達物質の遊離が亢進し、血管内の受容体との結合が活性化されれば、アレルギー性・非アレルギー性の機序を問わず、蕁麻疹は発症すると考えうる。さらに、Championの統計では、全体の72%が特発性蕁麻疹に属するとの結果が得られている。特発性蕁麻疹とは、もともと蕁麻疹を生じやすい体質に、肉体的な疲労や精神的なストレスが加わることによって、症状が引き起こされると考えられており、非特異的な誘因による蕁麻疹である。血液検査などを行っても大した異常は見当たらない場合が大部分であり、そのため日本皮膚科学会作成「蕁麻疹診療ガイドライン」においても、"すべての蕁麻疹症例に対して一律に1型アレルギーや一般的生化学検査等を行うべきでない"と述べられている。
4.蕁麻疹の治療
日本皮膚科学会作成「蕁麻疹診療ガイドライン」では、表2のような特発性蕁麻疹に対する薬物治療手順を示している。第一選択薬は当然、抗ヒスタミン薬であるが、ヒスタミン遊離活性の亢進は慢性蕁麻疹の約50%程度にしか認められないとの見解も認められており、そのためH1抗ヒスタミン薬の内服薬だけでは膨疹の出現を完全には抑制できない慢性蕁麻疹症例も少なからず存在している。反面、皮膚に存在しているヒスタミン受容体のうちの約15%はH2受容体であるため、蕁麻疹患者に対するH1+H2拮抗薬の併用は、H1抗ヒスタミン薬単独投与の場合と比べてヒスタミン誘発性の膨疹形成の抑制により有効であるとの説や、特に自己免疫的な機序の慢性蕁麻疹に対して、抗ロイコトリエン剤を抗ヒスタミン剤に追加すると有効性が高まるとの説が存在している。そのため、筆者は、H1抗ヒスタミン薬を服用しても抑制できない慢性蕁麻疹患者に対して、経験的にではあるが、1)まず、【1】H2拮抗薬、【2】抗ロイコトリエン薬、または【3】その両者、を抗ヒスタミン薬と併用する、2)それでも無効な場合には内服している抗ヒスタミン薬を倍量に増量する、ことにより、かなりの比率の慢性蕁麻疹症例に対して膨疹の出現を抑制しうるのではないかと考えている。いずれにしても、抗ヒスタミン薬の効果が乏しい蕁麻疹症例に対して、セレスタミン®などステロイド配合剤を容易に処方している場合をきわめて多く経験するが、安易にステロイド配合剤による治療を行うことは戒めるべきことであろう。ところが、2012年にKaplanは、抗ヒスタミン薬に抵抗する慢性蕁麻疹症例に対してH2拮抗薬と抗ロイコトリエン薬を加えても治療効果は乏しく、このような場合に最も有効な薬剤はシクロスポリンおよびオマリズマブであり、シクロスポリンとオマリズマブとを併用した場合、治療に抵抗する症例は5%未満であったとの新知見を報告している。従って、1)H1抗ヒスタミン薬にH2拮抗薬・抗ロイコトリエン薬の追加による改善度に関する検討、2)シクロスポリン・オマリズマブの治療効果に関する症例集積、が蕁麻疹の治療法に関する今後の課題であると思われる。
(3月14日 薬科部研究会より)