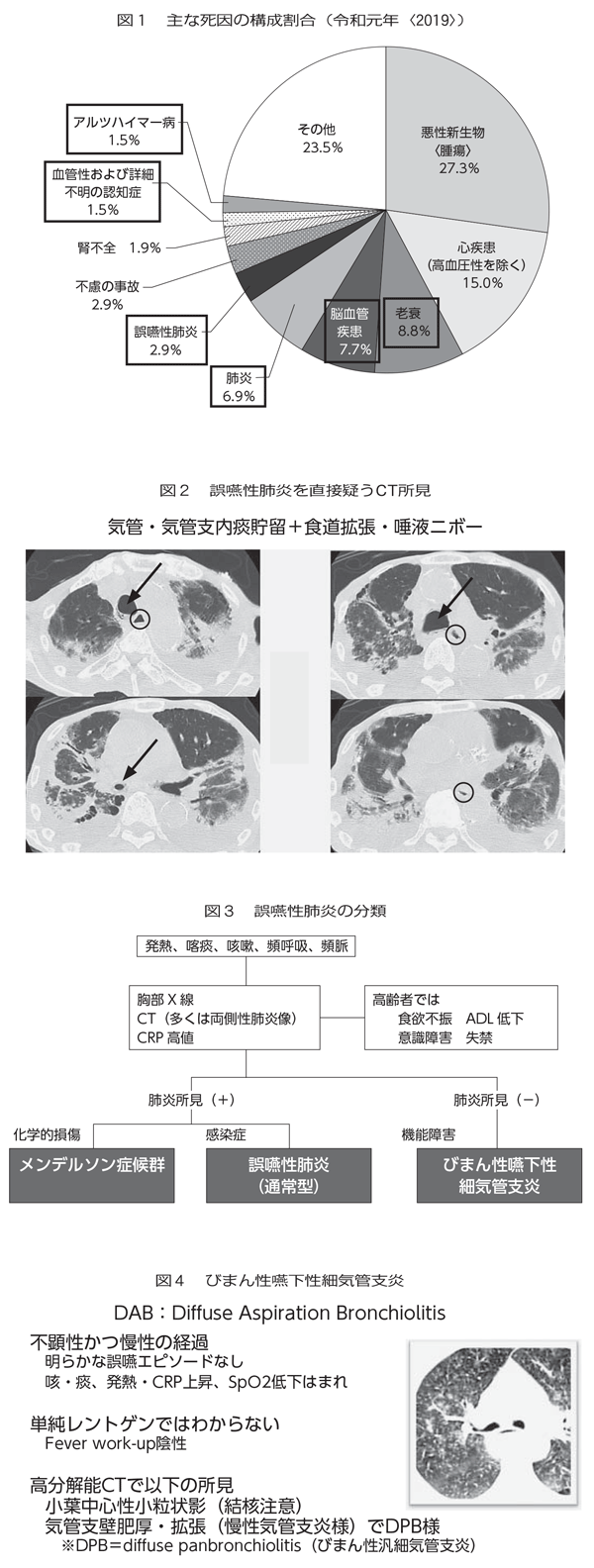医科2021.06.12 講演
誤嚥性肺炎を深く正しく診る
総合内科×リハ医学の視点から(上)
[診内研より523] (2021年6月12日)
札幌医科大学 総合診療医学講座 佐藤 健太先生講演
誤嚥性肺炎との出会い
私の研修歴を振り返ってみると、誤嚥性肺炎の重要性を認識し、ある程度ちゃんと診られると思えるようになるまでは10年程度かかってしまった。研修医時代は大病院での救急・急性期診療が中心であり、診断学や感染症診療に夢中だった。一方で、起炎菌が絞れず、治療してもスッキリ元気にはならない高齢者の誤嚥性肺炎は好きになれなかった。その後、家庭医療学と出会い、患者の心理・社会的問題までカバーできるようになり、病棟から退院したあとも外来で継続的に関わるようになり守備範囲は一気に広がった。しかし、それでも「食べられず体力もつかない患者」の消耗戦にも似た感覚には、正直なところ苦手意識を拭えないままだった。
いつしか研修医の肩書が外れ、亜急性期~慢性期の病棟や訪問診療で「肺炎が治った後の患者」の主治医として年単位で継続的に担当するようになった。そのような診療セッティングでは、嚥下障害を抱えたまま味気ない食事(ときには経管栄養)のまま数年過ごし、いつしか衰弱して亡くなっていく患者が非常に多く「なんとかしたい」と思うようになった。
幸い、そのタイミングでリハビリテーション医学を教えてくれる指導医に出会うことができ、ある程度はリハ医のいない環境での誤嚥性肺炎の診断と治療ができるようになった。しかし、そこに至るまでの10年間に「苦手意識を持ちながら流してしまった」患者たちがたくさんいることを思い返すと、いまでもなんとも言えない気持ちになる。
誤嚥性肺炎はCommon disease
誤嚥性肺炎への苦手意識を払拭すべく、まずは自身がいた病棟の統計や、日本全体の死亡・入院・身体障害の原因などのデータを調べてみると、「誤嚥性肺炎は非常にCommon」であることがわかってきた。当時の総合診療系の病棟の入院理由では、感染症が非常に多かったが、その中でも誤嚥性肺炎の割合はかなり高いことが共通していた。また、日本人の死因(図1)の上位に「肺炎」があり、この数年は集計方法が代わったため「誤嚥性肺炎」が6位にまで上昇している。
それ以外にも誤嚥性とつかない「肺炎」死亡の中にも未診断の誤嚥性肺炎は含まれているだろうし、老衰・脳血管疾患や認知症関連疾患で死亡した患者の多くも最期は誤嚥性肺炎を繰り返すことは多く「日本人の多くは、誤嚥性肺炎と付き合いながら消耗し、苦痛を感じながら、亡くなっていく」ことが見えてきた。
私個人の信念として、総合診療医は高度な診断推論スキルが使えるとか、あらゆる手技・処置が実施できるとかではなく「その地域で多くの住民を苦しめているCommon diseaseを的確に診療できること(Commonな問題については苦手領域がないこと)」を重視している。そんな私が、普通の市中肺炎の知識の延長や、感染症の基本原則の応用だけで、なんとなく誤嚥性肺炎を流して診ていたと気づいた時には大きな衝撃を受けた。
高齢者の誤嚥性肺炎を見つけるのは難しい
誤嚥性肺炎がCommonで重要だという認識は持てたものの、どの肺炎が「誤嚥性肺炎」なのかを見抜くのは非常に難しいことも同時に認識した。高齢者では典型的な呼吸器症状が出にくく、バイタルサインも動きにくく、しかし突然呼吸不全となってバタバタと対応することが多い印象だった。しかし、近年では高齢者での身体診察や画像所見についての知見が蓄積されてきており、「高齢者」ならではの特性や「誤嚥性」らしい特徴がわかってきて、「知っていれば診断は難しくない」と言えるようになってきた。詳細は推奨図書1)をご参照いただきたいが、高齢者の肺炎では咳と痰は出にくいものの、呼吸困難感や頻呼吸は比較的出やすく、意識障害や倦怠感も出やすい。Cracklesも高齢者になると偽陰性・偽陽性とも増えてくるが、体位やCracklesの回数などに着目することである程度検出可能となる。また、誤嚥を示唆するCT所見として、浸潤影の分布だけでなく気道内単貯留なども参考にすると良い(図2)。
また、日本呼吸器学会の誤嚥性肺炎の解説資料2)(図3)には、いわゆる誤嚥性肺炎(Aspiration pneumonia)と誤嚥性肺臓炎(Aspiration pneumonitis、メンデルソン症候群)の他に、びまん性誤嚥性細気管支炎(DAB: Diffuse aspiration bronchiolitis)が紹介されている(図4)。これは、まとまった量の誤嚥による大葉性肺炎や気管支肺炎ではなく、唾液の不顕性誤嚥が持続することによって気管・気管支壁に慢性炎症が起こることで慢性気管支炎のような病態を呈し、CTを撮ると気道撒布性の小粒状影が散在し、細気管支炎を起こしていることがわかる。このような病態では「食事でむせた」という顕性誤嚥のエピソードは指摘しがたく、血液検査での炎症反応や単純X線での浸潤影指摘は困難である。
DABの早期の段階で口腔ケアなどの嚥下障害治療を始めれば病態を食い止めることが可能だが、気づくことができなければ徐々に慢性炎症で消耗して、嚥下機能はさらに悪化し、どこかの時点で「突然発症したように見える」肺炎で急変してしまう。現代の超高齢社会で「なんとなく活気が悪い、呼吸器系が不安定な高齢者」をみたらDABを想起することが重要と考えられる。(つづく)
参考文献
1)上田剛士.高齢者診療で身体診察を強力な武器にするためのエビデンス 第2版.シーニュ. 20202)日本呼吸器学会."誤嚥性肺炎".2017年6月15日.https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=11(最終アクセス2021年6月12日)