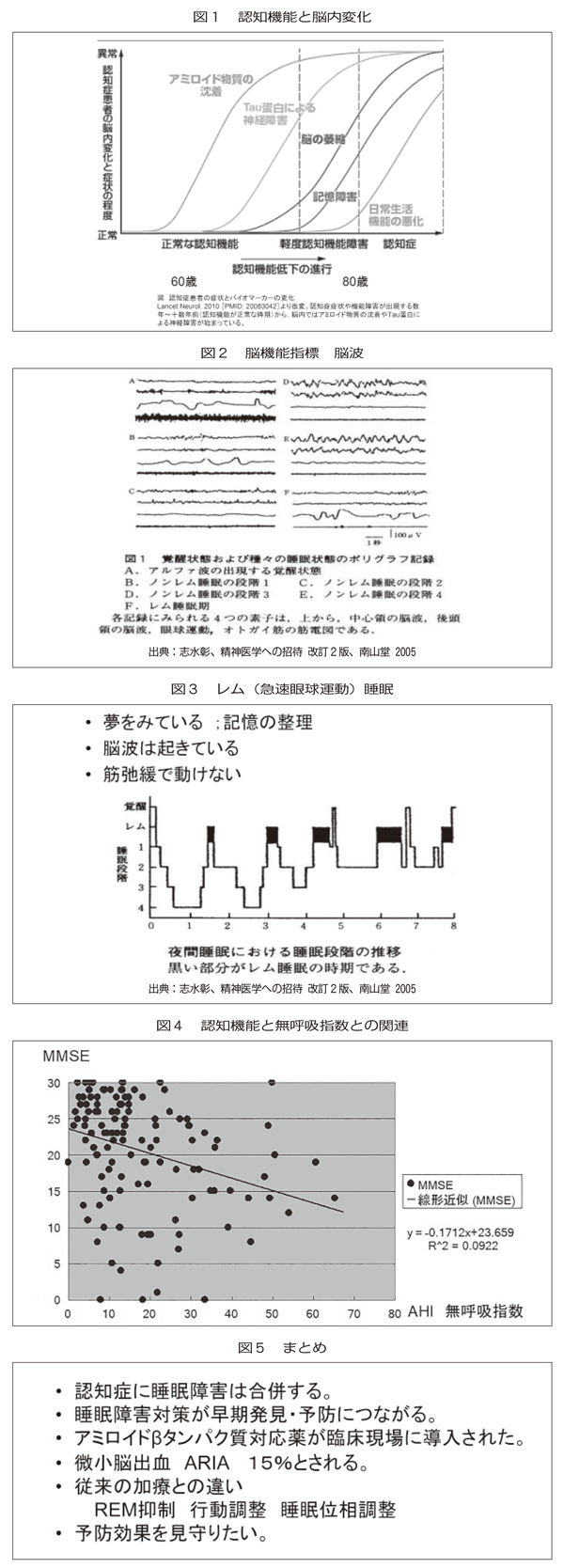医科2024.10.27 講演
第33回日常診療経験交流会演題より -保険診療のてびき・774-
日常診療における認知機能障害と睡眠障害について(2024年10月27日)
太子町・室井メディカルオフィス 院長 高森 信岳先生講演
認知機能と脳内変化
認知症周辺症状は在宅、施設での日常診療で苦慮する。その代表疾患であるアルツハイマー病はアミロイドβタンパク質、タウタンパク質の脳内での蓄積が関連するといわれる。記憶障害が現れる数十年前からアミロイドβタンパク質、タウタンパク質の蓄積が始まり、約10年遅れて脳萎縮が生じるといわれる。微小管結合タンパク質の一つであるタウタンパク質がリン酸化されて、細胞質中で線維化・凝集する神経原線維変化(タウ病理)の形成、神経細胞死に至るという「アミロイドカスケード仮説」が支持されている(図1)。
これらのタンパク質の蓄積に睡眠が関連する。睡眠が脳内におけるアミロイドβタンパク質の産生・排出と関わる。レビー小体型認知症についても発症前からの睡眠障害が知られている。
認知症の診断
認知症の診断は神経心理検査HDSR、MMSEをもちいて認知機能を評価する。一般的に20/30が検査のカットオフ値とされる。近年、道路交通法で高齢者の運転適性試験で標準化されている。次に頭部画像診断で形態学判断を行う。脳萎縮の部位、側頭葉内側面、頭頂葉の変化、血管病変など総合的に行う。認知症の診断は除外診断が原則とされる。
レム睡眠の関係する睡眠障害
睡眠障害の評価としてはPSG検査で脳波・眼球運動、心電図、筋電図呼吸曲線、いびき・動脈血酸素飽和度、体位などが評価される。睡眠脳波で判別すると、ヒトの睡眠はノンレム睡眠(non-REM sleep)とレム睡眠(REM sleep)という質的に異なる二つの睡眠段階に分類される。睡眠の深さ(脳波の周波数8-10Hzのα波、より遅いθ、δ波)によってステージ1~4(浅い→深い)の4段階に分けられる。ステージ1では頭蓋頂一過性鋭波、ステージ2では睡眠紡錘波およびK複合、ステージ3,4では高振幅徐波が出現する。ステージ3,4の段階は徐波睡眠(slow wave sleep, SWS)とよばれる(図2)。ノンレム-レム睡眠周期は90~120分間で、後半に進むにしたがいノンレム睡眠の持続は短くなり、睡眠徐波の出現は減少する。
レム睡眠は、急速眼球運動と骨格筋活動の低下を特徴とする。レム睡眠中には夢をよく見ると言われる(図3)。
レム睡眠行動障害は、睡眠中に突然、大声の寝言や奇声を発するもの。レム睡眠中は筋肉の緊張を低下させる神経調節が働くため、夢の中で行動しても、実際には身体は動かない。レム睡眠行動障害は、この筋肉の緊張を下げる神経調節システムが障害されることにより、夢の中での行動がそのまま寝言や体動として現れる。
レム睡眠行動障害は、50歳以降の男性に多く、加齢に伴い増加するとされる。パーキンソン病、レビー小体型認知症、多系統萎縮症といった神経疾患と関係すると考えられている。レム睡眠に影響する抗うつ薬が関係して起こる場合もある。レム睡眠の関係する睡眠障害として、ナルコレプシー、レム睡眠行動障害などが知られている。
他の睡眠障害は、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、睡眠時周期性四肢運動障害、薬剤惹起性睡眠障害、原発性不眠症などに分類される。PSGで幻視、意識障害、睡眠位相の変化などが可視化される。
臨床現場における認知機能障害と睡眠障害
当院における認知機能障害と睡眠障害について報告する。対象は65歳から97歳までの当院に入院された98人である。認知機能検査としてMMSE、FAB、SDSを施行した。無呼吸指数と認知機能については相関関係を認めた(図4)。アミロイドβタンパク質対応薬が臨床現場に導入された。当院でも導入予定である。アミロイドβタンパク質対応薬は適応が限られている。従来の加療との違い、予防効果を見守りたい(図5)。
質疑応答を受けて
フロアーからの質疑は、アルツハイマー病の発症は睡眠障害でのアミロイド排泄障害が先なのか、アミロイド病変が睡眠障害を誘発するのかどちらが本質なのかという鋭い質問であった。2000年以降アミロイド仮説に基づいて多数の治験開発が行われ、アミロイド抗体薬が実際に臨床現場で使えるようになった。
アミロイドPET、SPECT DATscan、シンチグラム含む核医学検査は実施施設が限られること、費用が高額であることで日常診療としてはかなりハードルが高い。
今回使用した、PSG検査は在宅で実施できる機材が開発された。自動解析ソフトの精度があがってきたこと、睡眠障害の治療としてCPAP、マウスピース、薬物療法、認知行動療法は医師、歯科医師、看護、リハビリ、介護等多職種連携のツールとして紹介させていただいた。
歯科の先生からも睡眠障害でのマウスピースの有効性を教えていただいた。
(2024年10月27日、第33回日常診療経験交流会演題より)
※第33回日常診療経験交流会の報告集を発行しています。ご注文は、電話078-393-1840まで