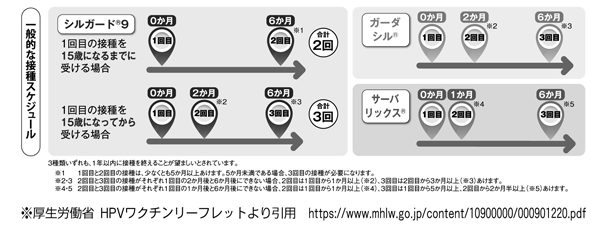医科2025.03.22 講演
[保険診療のてびき]
性感染症の検査と治療法アップデート(2025年3月22日)
淀川キリスト教病院 産婦人科医長 柴田 綾子先生講演
性感染症は「まれにみる疾患」や「恥ずかしい病気」ではなく、どこにでも誰にでも起こり得る身近な問題です。医療従事者は患者さんへ偏見をもつことなく、中立的な立場から正確な情報提供を行う必要があります。1.クラミジア・淋菌
クラミジア感染女性の90%近く、淋菌感染女性の50%以上が無症状という報告もあり、無症状であっても感染は除外できません。臨床現場では、性活動のある方に帯下異常、会陰のかゆみ、不正出血、腹痛、発熱、咽頭痛などがある場合は検査を提案します。検査は、クラミジア・淋菌の核酸増幅法検査(PCR法、SDA法、TMA法)で、子宮頸管粘液、帯下、尿などで検査します。血液検査によるクラミジアの抗体検査(IgG、IgA)は、治療後も陽性が持続し現在の感染を診断できないため推奨されていません。検査が陽性の場合は、パートナーも検査・治療が必要なことを必ず説明し、治療が終了するまでは、性行為を延期するかコンドームを着用することを推奨します。
〈クラミジアの治療薬〉
・ドキシサイクリン(100) 1日2回 7日間
・アジスロマイシン(ジスロマックR)(250) 1回4錠単回投与
・レボフロキサシン(クラビットR)(500) 1回1錠1日1回 7日間
〈淋菌の治療薬〉
・セフトリアキソン(ロセフィンR) 1g単回静脈投与
2.性器ヘルペス・尖圭コンジローマ
陰部の痛みでは性器ヘルペス、ブツブツでは尖圭コンジローマや梅毒を鑑別にあげます。これらは陰茎以外の皮膚にも存在するためコンドームでは100%予防できません。また治療後も神経根や皮膚に潜伏しつづけるため、数年後に再発するリスクがあります。〈性器ヘルペスの治療薬〉
・アシクロビル(ゾビラックス) 200㎎?5T/5 5日間
・バラシクロビル(バルトレックス) 500㎎?2T/2 5日間
・ファムシクロビル(ファムビル) 250㎎?3T/3 5日間
〈尖圭コンジローマの治療〉
・イミキモドクリーム(ベセルナクリーム) 1日1回 週3回
・レーザー凝固、液体窒素凍結、手術による切除
3.梅毒
2024年の梅毒患者報告数は14,663人と過去25年間で最多です。女性は20代で多く、男性では20~50代で感染者が多いです。潜伏期間が10~90日と長く、無症状で進行してしまうこともあります。性器の潰瘍、口腔粘膜のブツブツや咽頭炎、手や足の裏の皮疹、発熱などで鑑別に上げます。〈梅毒の治療薬〉
ベンジルペニシリンベンザチン水和物(ステルイズR)が2022年1月に発売されました。大人は1回240万単位(薬価10,025円)で早期梅毒(感染から1年未満)では1回筋肉注射、後期梅毒では週1回、合計3回筋肉注射で投与します。
4.トリコモナス腟症
帯下の増加や臭いの異常で来院することが多い。・メトロニダゾール(フラジールR)(250) 1回1錠1日2回 10日間
・フラジールR腟錠(250) 1回1錠1日1回 7~10日間腟内投与
5.帯下異常の治療
細菌性腟症、カンジダ外陰腟炎は性感染症ではありません。内服薬または腟剤の自己挿入等で治療を行い、症状が改善すれば治療終了です。高齢者の場合は、介護者が非滅菌手袋を使用し腟剤を挿入します。〈細菌性腟症の治療薬〉
・フラジール-R内服錠(250) 1回2錠1日2回 7日間内服
・フラジールR腟錠(250) 1回1錠1日1回 7~10日間腟内投与
〈カンジダ外陰腟炎の治療薬〉
糖尿病患者、妊婦、抗生剤使用後に発症しやすい。再発時には市販薬が使用できます。
・クロトリマゾール(エンペシドR1%)クリーム 1日2~3回塗布5~7日間
・イソコナゾール(アデスタンR)腟剤(300) 1回2錠 1週間に1回
・フルコナゾール(ジフルカンカプセルR)(50) 1回3錠 内服単回
6.患者説明
外陰部のかゆみや帯下異常では、不適切な石鹸や下着/ナプキンの使用により接触性皮膚炎がおきていることもあるため、以下のアドバイスを行う。・外陰部・腟はデリケートなため石鹸等で洗いすぎないようにする
・ナプキン/タンポンを長時間着けていると蒸れるのでこまめに変える
・きつい下着やパンツを通気性のよいものに変える。
7.HPVワクチン
HPV(ヒトパピローマウイルス)は、子宮頸がん・肛門がん・中咽頭癌のリスクとなる性感染症ですが、コンドームでは完全に感染予防できません。HPVワクチンは、日本では約12~16歳女性(小学校6年~高校1年相当)は定期接種(無料)で、17~27歳の女性(1997~2008年4月1日生まれ)はキャッチアップ接種で無料です(ただし2025年3月31日で終了)。自費接種の平均的な価格は、2価と4価では1回約1.5~1.7万円、9価は1回約3.3~3.6万円です(表)。
・接種方法とタイミング
HPVワクチンは新型コロナウイルスのワクチンと同様に筋肉注射となります。筋肉注射では逆血の確認は不要で、接種部位は揉まないようにします。痛みや緊張による迷走神経反射や気分不良がでることがあるため、背もたれのある椅子に座位またはベッド上に仰臥位で接種するのがおすすめです。ワクチン接種後の数日間は接種部位の発赤や痛みが出る可能性があります。9価HPVワクチンでは、1回目を15歳までに接種すれば2回で接種は完了します(図)。
・予防接種ストレス関連反応
予防接種ストレス関連反応(ISRR:Immunization Stress-Related Responses)とは、予防接種に関連したストレス・緊張などが原因で起こる症状で、①急性反応(血管迷走神経反射)と②遅発性反応(脱力や非てんかん発作などの解離性神経症状反応)があります。10代に多く、注射に対する恐怖心や不安などもリスクとなります。ワクチン接種に携わる医療従事者は、アナフィラキシー症状への対応に加えてISRRを予防するための配慮や工夫を行う必要があります。
HPVワクチン接種後に原因不明の症状が出現し、症状に改善が見られなかったり、精査が必要なときは各県にある「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を紹介することができます。
(3月22日、薬科部研究会より)
表 日本のHPVワクチンの種類
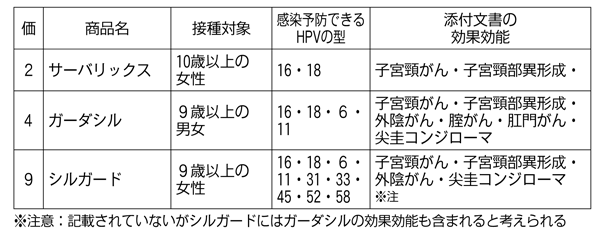
図 HPVワクチンの接種間隔