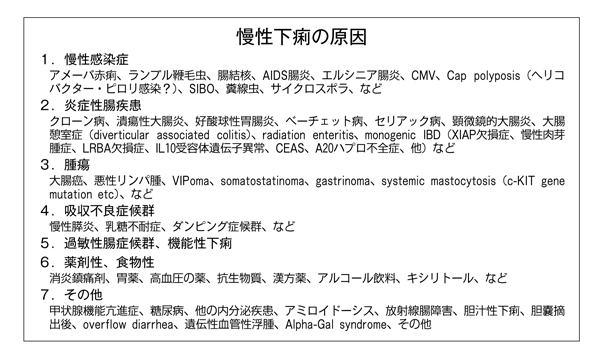医科2025.06.21 講演
[保険診療のてびき]
下痢の原因と薬物療法
-下痢止めの長期処方が続いているときに考えること-(2025年6月21日)
兵庫県立はりま姫路総合医療センター院長 木下 芳一先生講演
はじめに
下痢とは便の中の水分量が増加した状態を示し、便中水分量が80%を超えると泥状便となり、90%を超えると水様便となる。下痢では排便回数も増加することが多い。下痢は3~4週間以内に下痢状態が寛解する急性下痢と、3~4週間以上にわたって継続する慢性下痢に分けることができる。急性下痢と慢性下痢ではその原因が異なり、対処法も違ってくる。
急性下痢
急性下痢の原因は腸管感染症、薬剤性、食物に対するアレルギー、中毒、暴飲暴食などが多い。最も頻度が高いものは腸管感染症で薬剤性のものがこれに続く。腸管感染症には細菌性のものとウイルス性のものがあるが、細菌感染は大腸や回盲部に起こりやすく、ウイルス感染は小腸に起こりやすい。このためカンピロバクターなどの細菌感染性下痢は、大腸の損傷に伴って下痢が起こり下痢便の量は少なく血便を伴うことがある。腹痛や発熱症状が強く、反対に嘔気・嘔吐の症状は弱い。一方、ノロウイルスなどウイルス感染では下痢便の量が多く、腹痛や発熱は弱く血便もない。嘔気・嘔吐の症状は強い。このように腸管感染症による下痢では症状や便性状によって原因病原微生物を推定することが可能である。日本ではカンピロバクターが最も多い感染性下痢の原因であると報告されている。
感染性下痢に次いで薬剤性の急性下痢が多い。抗がん剤や抗菌薬、免疫抑制薬などは下痢の原因となりやすいことがよく知られている。ただし、これら以外にも多くの薬剤が下痢の原因となり、薬剤の副作用の7%は下痢であるとする報告がある。
急性下痢の治療では下痢に伴う脱水や電解質バランスの異常を補正しつつ原因を迅速に同定し、原因を取り除くことが治療の基本となる。不用意に下痢止めを投薬すると、下痢によって腸管内の有害物質を排出するというヒトの自己防衛機能を低下させることになり、感染性下痢であった場合には病原微生物や毒素を腸管内に長時間滞留させることになるため注意が必要である。
慢性下痢
有病率と原因
下痢症状が3~4週間以上継続する慢性下痢の有病率は1~5%程度と報告されており、慢性便秘よりは少ないがよく経験する病態である。慢性下痢の原因は急性下痢よりも複雑で多種類の原因が考えられる。
さらに、慢性下痢の原因となる疾患には厚生労働省の指定難病や腫瘍性疾患が多く含まれており、その対応には迅速性と正確性が求められる(表)。重篤な経過をとりうる原因疾患を見落とさないために、慢性下痢の診療においては注意深い鑑別診断が必要で、一般的な治療に反応しない場合は専門医にコンサルトすることが望ましい。
薬剤起因性慢性下痢
慢性下痢の原因の中で薬剤起因性下痢は重要である。実際、慢性下痢症の4%は薬剤起因性のものであると報告されており、慢性下痢患者の25人に1人は薬剤が原因となっている。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、プロトンポンプ阻害薬(PPI)、アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)などは顕微鏡的大腸炎を起こし下痢の原因となることがある。山梔子を含む加味逍遙散などの漢方薬は腸間膜静脈硬化症の原因となり下痢や腹痛の原因となることがある。消化管運動機能改善薬やプロスタグランディン製剤も下痢を起こしやすい。薬剤以外にもアルコール飲料、キシリトールやソルビトール、玉ねぎやニンニクなどFODMAPsを多く含む食品も下痢を起こしやすい。
内視鏡検査が有用な慢性下痢
慢性下痢の原因が病歴や身体診察、便・血液検査などを行っても確定できない時には大腸内視鏡検査が行われることが多い。ただし、大腸内視鏡検査で慢性下痢の原因が確定するのは5~31%程度であると報告されており、決して高いものではない。慢性下痢の原因としてクローン病や潰瘍性大腸炎などは内視鏡検査で異常が見つかることが多い。一方、好酸球性胃腸炎や顕微鏡的大腸炎、アミロイドーシスなどは内視鏡検査で異常が同定されることは少ないが、腸管粘膜の生検診断を併用すると診断を確定しやすい。画像診断が有効な慢性下痢
下痢型過敏性腸症候群、胆汁性下痢症、慢性膵炎、VIPomaや甲状腺機能亢進症などの内分泌性下痢では大腸内視鏡検査を実施し、さらに生検を実施しても異常を見出すことはできない。一方、CT、MRI、超音波検査などの画像診断を行うと慢性下痢の原因が確定することがある。慢性下痢の原因確定のための画像診断の有用性は4%程度であることが報告されており、慢性膵炎やVIPomaなどでは有効な検査となると考えられる。
下痢型過敏性腸症候群と胆汁性下痢
便・血液検査、大腸内視鏡検査と生検、CTなどの画像診断を行っても異常が明確でない慢性下痢の患者では下痢型過敏性腸症候群と診断されることが多い。ところが、下痢型過敏性腸症候群と診断された患者の約30%は下痢型過敏性腸症候群ではなく胆汁性下痢であることが報告されている。下痢型過敏性腸症候群では腹痛が強いが、胆汁性下痢では腹痛はそれほど強くはない。胆汁性下痢の病態は回腸終末部での胆汁酸の再吸収が低下し、胆汁酸が大腸に大量に流入することにある。再吸収障害のために胆汁酸の腸肝循環による再利用ができなくなり肝臓での胆汁酸の新生が亢進し、大腸内への胆汁酸流入がますます増加する。大腸内へ流入した胆汁酸は水分分泌と蠕動運動を亢進させ下痢を引き起こす。胆汁性下痢の有病率は一般人口の1~2%程度であると報告されている。胆汁性下痢はコレスチラミンやコレスチミドなどの胆汁酸吸着薬を内服することで1週間以内に下痢症状を消失させることが可能で、治療可能な慢性下痢として重要である。
まとめ
慢性下痢はその原因が多様であり、厚生労働省指定難病や悪性疾患が下痢の原因となることも少なくない。さらに、慢性下痢の4%は薬剤起因性のものであり、正確な原因の同定が重要である。大腸内視鏡検査を行って異常がなくても生検診断を併用すれば好酸球性胃腸炎や顕微鏡的大腸炎は確定診断に至りやすい。各種検査で異常が見つからない場合には下痢型過敏性腸症候群に加えて胆汁性下痢を忘れないことが重要である。(6月21日、薬科部研究会より)