2014年3月05日(1744号) ピックアップニュース
政策研究会 「社会保障の財源論−企業の内部留保をめぐって−」 小栗崇資氏 詳録
内部留保に課税し日本経済を立て直そう

【おぐり たかし】1950年愛知県生まれ。中央大学法学部卒業、明治大学大学院博士課程修了、商学博士。現在、駒澤大学経済学部教授、経済学部長。専門は財務会計論、経営分析論。
内部留保とは
内部留保という言葉を最近、マスコミが取り上げるようになった。私も2010年に『内部留保の経営分析−過剰蓄積の実態と活用』という著書を出版して以来、共同通信を始め多くの新聞や雑誌、テレビからの取材を受けるようになった。こうしたこともあり、皆さんも内部留保が270兆円あるということはご存じだと思う。私が出演したフジテレビの報道番組では、ディレクターから「いい内部留保と、悪い内部留保があるのですか」と質問を受けた。これは非常に分かりやすい質問だ。いい内部留保とは、将来の設備投資に回す資金や、雇用を増やすための資金などで、これが本来の自然な内部留保である。一方、現在、大企業に積み上がっている内部留保は、こうしたことに回らず、企業の本業とはかけ離れたマネーゲームの原資となるような過剰な資本蓄積で、これが悪い内部留保だ。
もう少し会計学的に整理すると、最も狭義の内部留保は利益剰余金のことで、利益のうち、社外流出分を除いて企業内部に蓄積された利益部分のことを言う。社外流出とは、配当金と以前は役員賞与のことを言っていた。現在では役員賞与は費用に含まれてしまっている。つまり、利益を株主と役員で山分けした後に残ったもののことを内部留保と言っていた。
広義の内部留保というと、一見、費用のように見える引当金も内部留保に含む。それは、将来に備えて利益を留保しているものだからであり、日銀や財務省の定義でもこうした引当金を内部留保に含んでいる。
また、企業が新株を発行した場合、それは全部資本金になるはずだが、現在の企業会計では、半分を資本金とし、残りの半分を資本準備金としている。この資本準備金は配当に使うことができ、利益と同じような扱いがされているので内部留保に含むことができる。
また、企業が保有する他の会社の社債や株式などの資産についてもその含み益は利益に近く、内部留保に含むことが適切である。
これらをすべて含んだ内部留保が広義の内部留保である(図1)。
この内部留保を公表しているのが財務省の「法人企業統計」である。政府が企業の内部留保を明らかにしていることは非常に大切で、さらに精度の高い数字を明らかにすべきだ。しかし、この法人企業統計には、ストックが明らかにされていないという問題もある。
そこで、各個別企業の内部留保を知るためには貸借対照表を確認する必要がある。貸借対照表の左側の資産には企業が調達した資金の運用形態が、右側には企業が調達した資金の源泉が記録される(図2)。この右側の純資産のうちの利益剰余金と資本剰余金、右側の負債の部のうちの長期負債性引当金、特別法上の引当金・準備金、資産の部の控除形式で計上される貸倒引当金を合計したものが、広義の内部留保といえる。
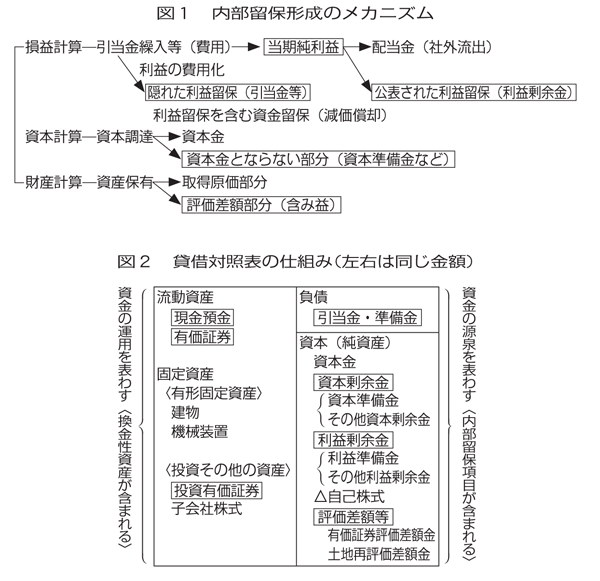
内部留保の推移
この内部留保がどうなっているのかを見ていく。2001年から2010年まで、法人企業統計で資本金10億円以上の大企業5500社の全資産合計の推移を、2001年と2010年で比べると591.4兆円から728.3兆円と1.23倍に増えている。この間、利益剰余金は84.7兆円から141.3兆円と1.66倍に増えている。資産の増え方に比べても内部留保の増加は大きい。これだけでは実態は分からない。企業会計は企業グループ全体でみる必要があるからだ。トヨタ自動車の子会社・関連会社は約700社もある。法人企業統計は1社1社の統計なので、本当の内部留保は分からない。では、どうすれば分かるのか。それはそれぞれの企業グループの連結財務諸表を分析するしかない。
これを分析したところ、上位20社だけで、利益剰余金が60兆円、上位100社では124.5兆円あることが分かった。上位100社だけで、法人企業統計の大会社5500社に匹敵する利益剰余金を抱えている。ここから推計すると上場企業3600社の利益剰余金は220兆円に上ると推計される。法人企業統計の数字がいかに実態を表していないのかということだ。
表1は総資産に占める利益剰余金の割合を1971年から2010年まで並べたもの。オイルショックなどで高度経済成長にブレーキがかかった1971年から1980年までの10年間をみると8.9%から8.6%と0.3ポイント減少している。バブル景気だった1981年から1990年をみると8.7%から12.0%と3.3ポイント増加している。その後の1991年から2000年をみると90年代不況といわれながらも12.3%から14.7%へと増えている。そして、2001年から2010年までデフレ不況が続いたが14.3%から19.8%へと5.5ポイントも増加している。実に2000年代は、バブル景気を上回る利益剰余金の増加があった。
ただ、このように内部留保が急増しているとしても、企業が成長して、設備投資や雇用に使われていれば問題ない。そこで、年代ごとに企業の総資産に占める有形固定資産(設備投資)と金融投資の割合を見てみると、1975年には有形固定資産が27.5%、金融投資が11.0%だったものが、2011年には有形固定資産が26.8%に対し、金融投資が34.0%と逆転している。
また、有形固定資産は割合だけでなくその金額も落ちている。企業が新たな設備投資をしない、減価償却をして、設備の入れ替えを行わないというのは異常な姿である。
一方で増えているのは金融投資だ。この金融投資は、貸借対照表の中で、有価証券と投資有価証券として計上されている。このうち有価証券というのは1年以内に売るもので、純粋に売買で儲けるための有価証券である。一方の、投資有価証券とは長期保有する株式や債券、子会社の株式などで、その株式や債券を売買して儲けるためのものではない。
純粋なマネーゲームに投じられている有価証券は、2001年から2010年までに7.6兆円から14.3兆円へと88.2%増となっているが、それでも金額は投資有価証券と比べればそれほど多くはない。投資有価証券は、2001年に86.8兆円だったものが、2010年には183.1兆円と110.9%増えている。その内訳を推計してみると長期的な金融投資が23.3兆円から56.2兆円へ、子会社投資が63.0兆円から126.9兆円に増えている。
これらは分けて考える必要がある。つまり、子会社をつくることで、子会社が設備投資を行っているということもありうるからだ。トヨタ自動車も本社で作っているのはたった8車種でほかの車種は子会社が製造している。トヨタ自動車の本社は設備投資していないかもしれないが、投資有価証券という形で子会社を保有し、その子会社が設備投資をしているから、この投資有価証券はマネーゲームには投じられていない。
しかし、現在の日本の大企業の子会社というのは本当にそれだけだろうか。日本企業の海外直接投資残高を日本銀行の統計で調べると、第1位と3位はアメリカ、中国だ。これは、理解できる。多くの企業がアメリカや中国に進出し、そこで子会社を設立し、製品の製造やマーケティングを行っている。しかし、第2位のオランダと第4位のケイマン諸島というのは、よくわからない。
実はオランダはEUの中でも最も法人税が低く、EUでの利益をオランダに持ち込んで管理している会社が多いのだ。さらに、ケイマン諸島はカリブ海の小さな島で、そこは法人税がない。それで世界中の会社がこの小さな島に従業員もオフィスもないペーパーカンパニーをつくってマネーゲームの拠点にしている。オリンパスの粉飾決算も、損失を隠すために、ケイマン諸島のペーパーカンパニーを通して、海外の会社を買収して損失を移し替える「飛ばし」という手法によって行われた。
つまり、海外や日本国内に子会社を設立し、その子会社が設備投資を行ったり、雇用を拡大したりして、グループとして事業を拡大している場合も、本社の貸借対照表には、子会社の株式が投資有価証券と計上されるため、それを活用可能な内部留保だというのは間違っている。しかし、現実には子会社といっても、マネーゲームの拠点であったり、税金を逃れて利益をプールするためのペーパーカンパニーである場合も多く、すべてを事業活動の実態があるととらえることはできない。
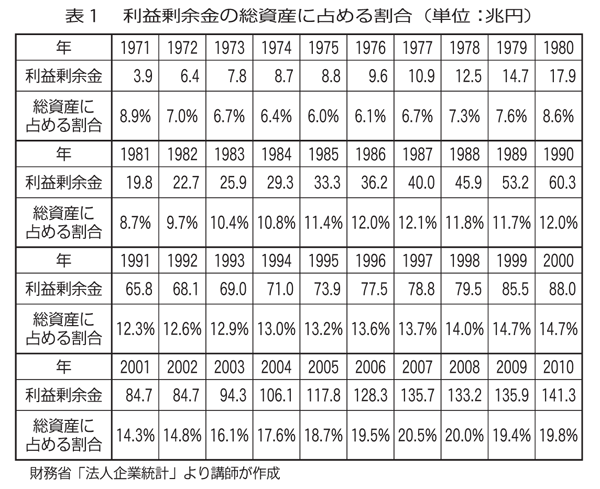
労働者の犠牲で増えた内部留保
さて、こうした内部留保はどのようにしてこれほどまでに膨張したのだろうか。その理由は二つある。一つ目は、人件費の抑制によるものだ。労働者の犠牲によって生み出されたといってもいい。2001年から2011年までに従業員給付は52兆円から51.4兆円へと1.2%減っている。従業員一人当たりの賃金で比較すると2001年の762万円から679万円へと11.1%減少している。仮に、2001年の給付水準が維持されていた場合と比較すると、10年間で21.1兆円もの従業員給付が抑制されたことになる。さらに、従業員給付が企業の総資産と同じ伸び率で推移した場合と比較すると、10年間で33.1兆円が抑制されたことになる。2001年から2011年までの内部留保の増加分は56.6兆円なので、その約4割から6割が人件費を抑制した結果生み出されたということもできる。
もし1999年から2000年にかけて起こった好景気の中で、きちんと従業員の賃金を引き上げていれば、自動車や液晶テレビがさらに売れて、もっと好景気を維持できたはずだ。しかし、1995年に日本経営者団体連盟(当時)が「新時代の『日本的経営』−挑戦すべき方向とその具体策」を発表し、それまでの年功序列賃金体系や終身雇用制を破壊し、正規労働を減らして、派遣労働などの非正規雇用を増やしてきた。その結果、従業員賃金は抑制され続け、その分が大企業の内部留保として積み上がっているのだ。
国民の犠牲で増えた内部留保
もう一つ、内部留保がここまで膨張した理由は法人税の減税だ。国は法人税減税の穴埋めとして、合わせて消費税増税を行ってきたのだから、国民の犠牲によって生み出されたということもできる。1989年に40.0%だった法人実効税率は、1999年には30.0%に引き下げられてしまった。2001年から2011年の10年間の法人税率がもし引き下げられていないとすると、96.3兆円となり実際の10年間の法人税額との差額は9.6兆円にも上る。さらに、法人実効税率は30.0%となっているが、これはあくまでも名目であり、租税特別措置などを考慮して計算すると実際の税率は24.17%から15.65%だと言われている(表2)(田中里美〈2012〉「税負担率の算定分析−法人税制と内部留保の拡大」『経済』)。その特別措置がなかったとすれば、企業は10.8兆円の法人税をさらに支払う必要があったといわれ、少なくとも10兆円程度が法人税減税によって内部留保になっているということができる。つまり、内部留保の5割から6割は人件費の抑制と法人税の減税で生み出されたものであるといえる。
企業が法人税減税を政府に強く求め、人件費を抑制して、内部留保を積み上げたのは、バブル崩壊以降の厳しい経済状況や、進むグローバル化に対する恐怖からで、1社1社をとればその判断は間違っていないかもしれない。だが全体で見れば、日本の内需を縮小し、日本経済からさらに力を奪うことになってしまった。
本来ならば、企業がそういう判断をしないようにするのは政府の役割のはずだが、90年代中盤から日本政府は「新自由主義」路線をとっている。これは、企業活動や市場に政府はなるべく介入しないという方針で、その方が富める者がさらに富むことができ、富める者が富めば、やがて富める者以外にも、富が滴り落ちるという理論だ。それで、政府は大企業のこうした誤りを正すことなく放置してきた。
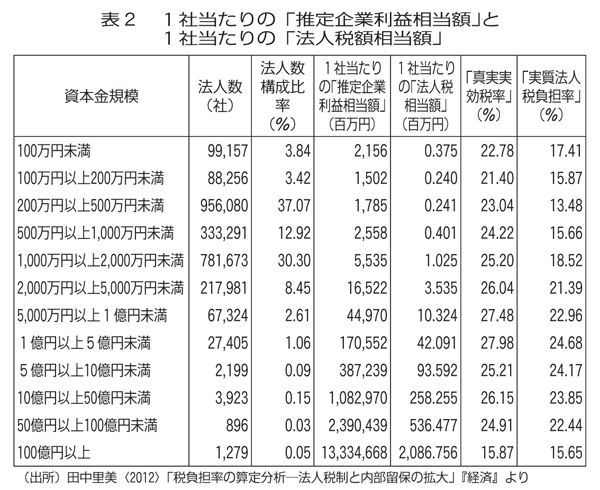
すぐ活用できる内部留保−換金性資産
3年前、日本経団連は国会で、内部留保を「設備投資に使っている」と証言した。しかし、先ほどからみたようにそれがでまかせだったことがわかった。しかし、日本経団連は内部留保について「すぐに現金化することはできず、活用は無理だ」とも証言した。これは本当だろうか。実際には、内部留保の中には換金性のものが多く含まれる。つまり、現金・預金や有価証券、自己株式だ。
この換金性資産は2001年には52.5兆円だ。それが2011年には80.4兆円にまで増えている。さらに、この換金性資産に投資有価証券のうち、子会社株式を除いたものを加算した額は2001年の68.3兆円から2011年には115.0兆円と68.4%も増加している。
この中には株式や債券が含まれているので、一度に売れば市場に混乱をもたらす。しかし、徐々に売ればそうしたリスクも回避できる。それに、最近では日本の大企業が保有する株式には、非常に多くの自社株が含まれている。
日本の上場会社3600社のうち、10大株主に自社が含まれている会社は4割にも上っている。自社が筆頭株主という極端な会社も200に上っている。これは株式会社の姿としても異常な姿だ。各社は自社株を購入することによって株高を演出している。さらに、自社株を購入し、株高を演出した上で、売却するという投資手法をとる企業も増えている。こうした内部留保は換金できると考えていい。
活用でGDP1.86%上昇
木地孝之慶應義塾大学商学部助教授は論文「大企業の内部留保をどう活用するか」(『経済』2012年9月号)の中で、2010年度の全企業の内部留保総額461.0兆円のうち245.7兆円を活用した場合の試算を明らかにしている。活用方法の内訳は、労働者の賃金を過去のピーク時まで戻すことに29.3兆円、サービス残業の根絶や有給休暇の完全取得など働くルールの確立に20.0兆円、有形固定資産を過去のピークに戻すための設備投資に28.5兆円、東日本大震災の復興投資に16.9兆円、国債の引き受けに151兆円というものだ。こうした活用を行うと、経済成長効果は国内総生産を178.5兆円押し上げ、11年間の平均でGDPを1.86%押し上げる効果があるとしている。また、直接466.1万人の雇用を生むとされ、2012年の完全失業者数315万人を吸収することが可能であるとしている。さらに間接的な雇用も含んだ雇用誘発効果は944.7万人にもおよぶとされている。また、こうした経済成長や雇用拡大による税収効果は15.3兆円増加するとされている。
この試算は中小企業の内部留保を含んでいるし、現在の内部留保の半分以上を活用するという点で問題があるが、一つのモデルとしては非常に有益な提案だ。
ただ、いきなり内部留保を取り崩させるのは難しい。
内部留保を社会的に還元する方法
大前提となるのが、社会的圧力で、企業に内部留保を賃金・雇用・国内投資へと振り向けさせることだ。そして、具体的には内部留保への課税を行う必要がある。
現在の法体系や税体系では会社、つまり法人の定義は法人擬制説によっている。株主が集まって法人たる会社を構成しているという考え方だ。しかし、そう考えると会社の利益は配当によって株主に分配されるのだから、株主が得た配当に所得税をかければよいことになるが、実際には配当前の利益から法人税が徴収されている。それについて法人擬制説の立場からは、法人税は所得課税の前取りだと説明される。会社の利益から法人税を徴収し、その残った利益が配当に回るのでその配当から所得税を徴収するという2段階の税制となっているのだ。
しかし、これまで説明したように日本の大企業は実際の法人税も低く、配当性向も低いので、莫大な内部留保が積み上がっている。そこで、法人税、配当への所得課税に追加して、残った内部留保にも第3段階の税として課税を行うことは理論的には可能である。
実際に、世界の国々ではこうした内部留保課税を導入している国もある。代表的なのは台湾だ。台湾では1998年から毎期の内部留保増加額に10%の課税を行っている。しかし、台湾企業の競争力はそれほど低下していない。それどころか、むしろ内部留保課税を嫌がる企業が配当を増やすため、株式市場が活況となり、アジアでも非常に人気のある株式市場となっている。
株式市場が活況になっても、庶民は潤わないという反論もあると思う。しかし、それは日本の個人の金融資産のあり方の問題だ。日本では個人の金融資産のうち約50%が預貯金で、株式や債券は15%だ。アメリカでは逆に、国民皆年金がないことも手伝って、50%が株式や債券で、15%が預貯金となっている。どちらも極端だが、日本ももう少し個人が株式や債券を保有して、企業の利益を国民のものにしてもいいのではないか。
この場合の株式投資というのは、短期売買で儲けるためではなく、長期保有して、安定的に配当や経済成長と企業の成長に裏付けられた値上がりを狙うものだ。
日本では、株式市場がアングラマネーの温床となったり、仕手筋など玄人筋が投機的な手法で株式市場を混乱させることが歴史的にあり、個人の市場参加が極端に少ないいびつな構造となっている。市場の透明性を高めて一般の国民がそれほどのリスクを負うことなく参入できるようにするべきだ。
また、日本でも同族会社とよばれる形式の会社には内部留保課税を行っている。同族会社とは家族が株式を持ち、経営権を持つ会社のことで、こうした会社で利益が上がっている場合、配当を行うと所得税がかかってしまうので、配当を行わず、さまざまな生活用品を会社の経費で購入する傾向が高い。それで、こうした特徴に着目して、内部留保課税を行っているのだ。日本でも一部の会社に内部留保課税を行っているのだから、他の大企業に行うことも可能なはずだ。
世界の例からも、日本の例からも、いずれにしても内部留保課税はそれほどおかしいことではない。例えば、台湾のように内部留保の増加分に10%の課税をした場合、2001年から10年間で5兆円の財源となる。これ自体は莫大な額ではないが、この間の法人減税分を穴埋めできる規模であり、波及効果として株式市場が活況となる可能性もある。
課税の方法としては、テクニカルな話になるが、利益剰余金の非課税戻し入れを提案したい。つまり、下請け支援や雇用拡大、賃金引き上げに利益剰余金を活用する場合は、その分を非課税にするというものである。
新たな「大企業」「中堅企業」を育てよう
内部留保活用の方法として設備投資誘導策をとることは重要だ。確かにアベノミクスでも、設備投資減税を行うとしているが、大企業向けだ。これまで自民党の経済政策は現在の大企業向けのものが中心だった。トヨタ自動車やキヤノンなど、電機、自動車などを積極的に海外移転させ、国際競争に勝てるように支援してきたが、それで起こったのは国内産業の空洞化だ。国内では多くの若者が正規雇用に就けなくて非常に苦労している。
だから、こうした企業支援策は無意味だ。既存の大企業を支援するのではなく、新たな大企業、中堅企業を育て、新しい産業を興すことが必要だ。大企業を優遇すれば下に富が流れて、日本経済全体がよくなるという成功体験はもう通用しなくなっている。実際、アベノミクスでは莫大な公共投資が計画されているが、すでに90年代に行われた大規模な公共投資では雇用効果が上がらないことが経済学的に実証されている。雇用効果が最もあるのは、介護、医療分野への投資だ。
また、新しい大企業、中堅企業を育てるためには、日本の地方の中小企業の技術力に注目すべきだ。東京都大田区では「江戸っ子1号」という深海探査艇を中小企業の技術を集めて開発している。東大阪の中小企業が協力して開発した「まいど1号」にヒントを得た取り組みだ。東大阪や大田区の中小企業には世界も驚くすばらしい技術がある。財界幹部の求める経済政策ではなく、こうした企業を支えていく必要がある。
そして、脱原発を進め再生可能エネルギー産業や福祉、医療、教育などの分野で新たな産業を育てる必要がある。内部留保の活用は万能薬ではない。しかし、大企業優位の政策の一角を崩して日本経済を立て直すためには役に立つ政策だ。



