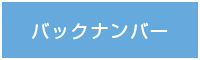2025年5月05日(2101号) ピックアップニュース
「保険でより良い歯科医療を」兵庫連絡会・市民学習会
子どもに必要な「ケア」阻む貧困をなくそう

藤原先生(手前)が日本の子どもの貧困問題を紹介した
藤原先生は、厚生労働省やOECD各国の統計データを示しながら、日本社会の貧困の特徴を紹介。「日本は所得中央値の半分以下で生活する人らの割合を示す『相対的貧困率』が15.4%と先進資本主義国10カ国中最も高い。特にひとり親世帯の貧困率は44.5%と、ワースト2位の韓国の36.9%を大きく引き離している。その上、母子世帯の就労率をみると86.3%と諸外国より頭抜けており 〝働いても貧困から抜けだせない〟という現状が見てとれる。政府の所得再分配の機能が果たされていないと言わざるを得ない」と指摘した。
また講師は、研究によって貧困との関連が立証されている子どもにおける様々な格差を紹介する中で「生活、自己肯定感、家族、健康、精神、交友など様々な面で経済状態が与える影響は大きく、健康面での口腔崩壊(むし歯が10本以上など咀嚼困難の状態)などもその表れの一つ」「税金を減らして一時の手取りを増やす政策が持てはやされているが、現代の日本において、真に必要なことは所得再分配による貧困削減効果を高めていく政策ではないか」と呼びかけた。
最後に講師は、生活時間の使い方の国際比較(1日24時間=1440分)を紹介する中で「日本と韓国男性が家事育児、介護、買い物などのアンペイドワークに使う時間は1日平均47分、49分と極めて低い。裏返せば『家事労働(子どものケアも含む)は女性が担って当たり前』の社会が続いている。また、ひとり親世帯の親が長時間労働の下に置かれるということは、それだけ子どもに必要なケアが欠如した社会ということになるのではないか」と問題提起した。
冨澤先生は、歯科における「手遅れ事例」を告発する『歯科酷書』から、全国の民医連の院所に寄せられた困難症例を紹介。「子どものう蝕が全体傾向として減っている一方で、口腔崩壊の子どもが散見され、歯科治療の必要な子らが必ずしも医療に繋がっていない実態がある。その原因は、社会的決定要因が複合的に絡まっている場合が多く、いつでも・どこでも・だれでもが必要な受診ができる社会を目指す必要がある」と署名を訴えた。
参加者からは「子どものケアが同居家族女性の仕事とされてきた背景には、男性がアンペイドワークを担わないことが標準化された社会があることがよく分かった」「詳細な統計から貧困問題の根深さがよくわかった」などの感想が出された。
冨澤先生が司会を兼任。終了後「無料歯の健康相談」を開催した。