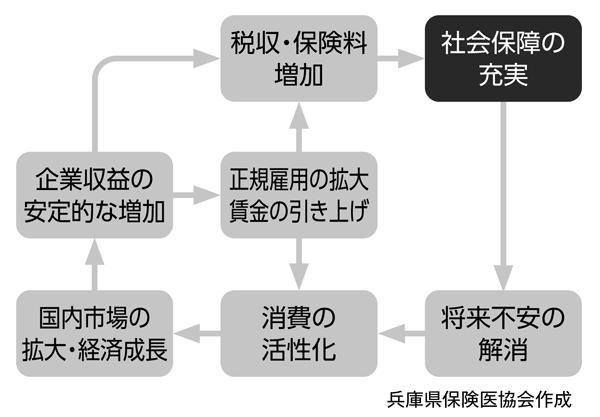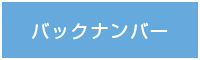2025年6月25日(2105号) ピックアップニュース
参院選特集 政策座談会 問われる医療と社会保障
社会保障拡充実現する党 見極めよう

司会 武村 義人 副理事長

木原 章雄 理事

川西 敏雄 参与
経費高騰に診療報酬追いつかず
西山 これまでの開業医人生の中で最も厳しい時期と言っても過言ではない。実際、保団連が全国37都道府県・4658件の医療機関を対象とした調査でも、2024年1月比で66%の施設が「収入が減少した」と回答し、光熱費や材料費、人件費の上昇に対し、92%が「診療報酬では補填できていない」と回答している。さらに、賃上げを実施した施設でも90%が「診療報酬ではカバーできない」との厳しい声が寄せられた。
永本 病院の経営も深刻だ。国立大学病院ですら42病院中25病院が赤字に陥っており、日本の医学研究や教育、高度医療の提供体制が維持できなくなる恐れもある。
森岡 報道によれば、すべての県立病院が2年連続で赤字となっており、「倒産寸前」との指摘もある。県は対策として130床規模の休床を打ち出したが、これでは県民に必要な医療を提供できなくなる恐れがある。
木原 長らく抑制されてきた診療報酬は、急激な物価上昇や人件費・医薬品費の高騰に対応できず、医療機器の更新を行う余力も奪われ、医療機関が本来果たすべき医療の質や安全性の維持が困難になっている。こうした状況を打開するには年度途中でも柔軟に診療報酬を引き上げる「期中改定」が必要不可欠であり、それを実現できる政党、候補が求められている。
「骨太」と財政審建議は医療費抑制を継続
川西 「骨太の方針2025」は、自民党の意見を反映し、「医療・介護等の現場の厳しい現状」と盛り込まれた。さらに、「高齢化による増加分に相当する伸びに...経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する」として、社会保障予算を高齢化による増加分に抑制する方針が転換され、物価上昇分も容認される方向性が示された。
永本 これまでに比べると、医療機関に一定の配慮を見せた部分もあるが、選挙が近いなか、自民党を支援する各医療団体の組織内候補に対するリップサービスとみるべきだろう。
西山 そもそも、「骨太の方針」では、「歳出改革」の文言が散見され、引き続き医療費抑制方針が打ち出されている。「建議」には診療報酬の「適正化」を名目に、再診料の包括化や外来管理加算の見直し、リフィル処方箋の拡大、検査・画像診断の使用適正化などが盛り込まれている。
川西 患者負担増にも警戒が必要だ。「骨太の方針」は、スイッチOTC薬の活用拡大や、高齢者の医療費自己負担割合の見直しを含む制度改変を視野に入れている。
急激な物価高騰が続く中で、自己負担が家計を圧迫し、受診を控える動きが全国的に広がっている。特に低所得層や高齢者世帯を中心に「受診抑制」が深刻化しており、健康状態の悪化や重症化を招く一因となっている。
保団連が行った25年の調査でも、「明らかに患者の来院が減っている」「高血圧や糖尿病の患者が薬を減らすよう求めてくる」といった声が相次ぎ、受診控えによる病状の進行や入院患者の重症度上昇が報告されている。こうした状況下で、患者負担増を強行すれば、患者の命と健康を危険にさらすことになりかねない。
森岡 病床の大規模削減にも注意が必要だ。自民・公明・維新の3党が合意した文書では、病床約11万床の削減方針について「その旨を骨太の方針に反映」と記載されている。実際には具体的な数字などは盛り込まれなかったが、注で「詳細については『自・公・維合意』を参照」と盛り込まれた。日本医師会をはじめとする主な病院団体もおおむね賛同していることは大きな問題だ。
木原 留意すべきは、野党の中に医療費抑制に前向きな政党が存在している点だ。自民・公明が後期高齢者の窓口負担増や保険給付範囲の縮小、病床削減、介護報酬引き締めなどを主導してきたのは当然としても、病床削減のように、維新も積極的に制度縮小に関与している。
維新は「医療費4兆円削減」方針を掲げ、OTC類似薬の保険給付除外(図1)、地域フォーミュラリ(標準薬剤選択リスト)の導入、病床11万床の削減、高齢者の窓口負担引き上げをめざすとしている。こうした政策により「現役世代の保険料を年6万円軽減できる」とアピールするが、その試算はいずれも粗く、医療アクセスの格差拡大、受診控え、医療の質低下を招くリスクが高い。医療提供体制の持続可能性や患者の健康権を大きく損なう危険性をはらんでいる。
西山 国民民主党の姿勢にも注意が必要だ。同党は生活者重視を掲げながらも、自己負担見直しや報酬効率化には一定の理解を示し、制度改悪に対して実質的に追認する立場を取っている。24年総選挙の選挙公約では「高額療養費制度の自己負担上限額について経済状況に応じた再設定を検討」を掲げていた。
武村 立憲、共産、れいわ、社民といった野党は、こうした改悪に対して一貫して反対の姿勢をとり、医療・介護の充実や、保険証の存続などを訴えている。ただし、立憲内部には財政保守的な傾向もあり、対応には揺らぎが見られる。共産とれいわは、制度改悪の根底にある財政偏重や競争導入の政治姿勢を厳しく批判し、必要な社会保障を保障する政策転換を強く求めている。
医療・介護を誰もが安心して受けられるものとするためには、各党の姿勢と過去の行動を的確に見極めることが、選挙を含む今後の政治選択において極めて重要である。
マイナ保険証 事実上の義務化と各党

西山 裕康 理事長

永本 浩 監事

森岡 芳雄 副理事長
まず、マイナンバーカードの取得が事実上強制され、任意取得を原則とする制度設計に反している。さらに、カードの他人への誤った紐付けや、資格情報の不一致など、個人情報保護上の深刻なリスクも露呈している。医療現場ではオンライン資格確認の義務化やカードリーダーの不具合などにより混乱が広がり、カード未所持者の受診が困難になる事例も報告されている。
森岡 各党の立場は明確に分かれている。自民、公明、維新、国民民主はマイナ保険証導入に積極的で、23年には健康保険証の廃止を盛り込んだ関連法案を成立させた。医療DXの推進や事務の効率化、なりすまし防止などを導入理由として挙げているが、保険証廃止を正当化する明確な根拠は乏しい。
一方、立憲は従来の保険証との選択制を主張し、25年1月には「保険証復活法案」を国会に提出している。共産や社民も、情報管理や憲法上の問題点を指摘しながら保険証存続を強く訴えている。
西山 国民皆保険制度の根幹に関わる重大な制度変更が、性急かつ一方的に進められている現状は深刻だ。国民の受療権や選択権を守るためには、拙速な義務化ではなく、制度の安全性と公平性を十分に確保した上で、丁寧な議論と合意形成が不可欠だ。
「社会保障のため」は本当か
消費税の逆進性を問う
消費税収は増税等により増えているが同時に政府は法人税減税や高額所得者への減税、軍事費の拡大などを進めてきた。結果として消費税によって得られた財源が大企業や富裕層への減税の穴埋めに使われてきたことは明らかだ。また、この間、医療・年金・介護の制度は削減・抑制される一方で、消費税率だけを引き上げており、社会保障の充実にはつながっていない。
永本 消費税は、所得の少ない人ほど重い負担を強いられる典型的な逆進性を持ち、とりわけ物価高が続くいま、家計を直撃している。高齢者や子育て世帯、非正規労働者など社会的弱者に過酷なこの税制は、社会保障を支えるどころか、むしろ「社会保障を必要とする人々の生活を蝕む構造」となっている。
木原 今こそ、消費税に依存しない別の財源構築が必要だ。大企業や富裕層への優遇を見直し、内部留保への課税や所得再分配の強化で、公平で持続可能な財源確保は十分に可能だ。こうした財政のあり方を、選挙を通じて国民が意思表示することが、今まさに求められている。
消費税減税や廃止を掲げる勢力に一票を託すことによって、本当に人間らしく生き、子どもを育める社会をつくるための転換点とすべきである。
武村 保団連は、社会保障の財源として消費税に依存する政府の方針に明確に反対している。応能負担を基本とした公平な税制への転換を提唱しており、防衛費の大幅増額についても「不要不急の支出」として厳しく批判し、一部を社会保障財源に振り向けるべきだと訴えている。
西山 消費税の減税や廃止は、医療機関の経営を直接的に支える重要な施策でもある。現在、医療機関は「控除対象外消費税」によって、仕入れ時に支払った消費税の多くを税務上控除できず、大きな負担を強いられている。近年の物価高騰や人件費上昇に伴って経費が増加し、この負担は大きく膨らんでいる。
消費税を減税、あるいは廃止することで、こうした問題は根本から解消される。これは地域医療の持続性を確保し、医療崩壊を防ぐための現実的かつ即効性のある経営支援策であり、早急に実行されるべきだ。
川西 いま日本社会が直面している最大の課題は、少子高齢化の進行と、それに伴う医療・介護・年金などの社会保障制度の持続可能性だ。
しかし政府は、「防衛力の抜本的強化」の名のもと、27年度までに防衛予算をGDP比2%(年間11兆円超)に倍増させる計画を進め、その財源確保のために、社会保障費の自然増圧縮、消費税の維持・強化、さらには復興増税の流用までを進めている。「人を守る」と言いながら、実際には人びとの生活と健康を脅かす矛盾した政策である。
今、必要なのは武器や基地ではなく、医師・看護師・介護職員・保育士といった「人を支える人材」への投資である。社会保障の充実を最優先とし、その財源は富裕層や大企業への課税の見直し、不要不急の軍事費の削減によって確保すべきである。米の減反政策と同じ過ちをおかしてはならない。
西山 一方で、現代貨幣理論(MMT)に基づく新たな財源論も注目されている。国家は自国通貨を発行できるため、歳入(税収)を財源としなければ支出ができないという従来の常識は成り立たず、社会保障やインフラなど、社会的に必要な公共支出は、税収や国債残高にとらわれず、積極的に実施すべきだという考え方だ。
武村 これには多くの批判もある。特に、市場や国民の「通貨への信認」を損ねるリスクが指摘されている。政府が無期限に通貨を発行し続ければ、国内外の投資家が通貨価値に疑念を持ち、通貨安・資本逃避・物価急騰といった副作用が起きかねない。とりわけエネルギーや食料を輸入に依存する国にとって、通貨価値の低下は致命的だ。
社会保障・財源をめぐる各党の立場
武村 各党は異なる財源論を掲げており、「消費税減税か否か」「防衛費拡大か縮小か」「財政規律か積極財政か」といった対立軸が明確になっている。有権者は、どの政党が命と暮らしを優先し、持続可能な経済運営と財政政策を実現するのかを見極めたうえで、投票行動を選択する必要がある。木原 まず、消費税については、共産とれいわは「廃止」を主張している。共産は消費税を「逆進性の強い悪税」と断じ、まずは税率5%への引き下げを提案。れいわは、消費税廃止によって可処分所得を増やし、内需拡大を通じて税収を回復できると主張する。
一方、立憲と国民民主は、消費税の引き下げやインボイス制度の見直しに言及はしているが、一時的な対応にとどまる。自民と維新は、消費税を社会保障の安定財源と位置づけ、維持または将来的な引き上げも視野に入れており、税率自体の見直しには否定的だ。
森岡 防衛費の扱いにも各党大きな違いがある。自民と維新は、防衛費GDP比2%超への引き上げの路線を推進・容認し、長距離ミサイルや敵基地攻撃能力の保有、防衛産業強化を積極的に進めている。国民民主もこの流れに一定の理解を示しつつ、費用対効果の検証を求める中間的立場だ。
これに対し、共産とれいわは防衛費拡大を厳しく批判し、軍事費を削減して社会保障や福祉に振り向けるべきだと主張している。立憲も歯止めのない軍拡に懸念を示し、「防衛より生活」という立場を取っている。
政治とカネ 問われる透明性と説明責任
永本 今回の選挙で外せないのは政治とカネの問題だ。近年の政界不信の象徴的重大課題であり、特に2023年末に明らかになった自民党旧安倍派などの派閥による不記載・キックバック問題は、政治資金規正法の形骸化を浮き彫りにし、国民の強い批判を浴びた。これを受けて政治資金規正法の見直しが国会で議論されたが、改正案の中身は各党で大きく異なり、「抜本改革」か、「看板の掛け替え」かが問われている。武村 自民は政治資金問題の当事者でありながら、提出した法案は「収支報告書へのキックバック記載義務化」「政策活動費の10年後開示」などにとどまり、企業・団体献金の禁止には踏み込まなかった。関係者の処分や説明責任も不十分だ。公明は、政策活動費の制限拡大など部分的な改革には言及するものの、自民党に歩調を合わせ、企業献金の禁止までは踏み込んでいない。
木原 維新は「企業・団体献金禁止」の旗を掲げるが、企業のパーティ券購入という形で事実上企業・団体献金を受け取っており、言行不一致だ。また、自民案に対して賛成姿勢を示すなど、改革への本気度には疑念が残る。国民民主も改革姿勢を打ち出しているが、企業献金の受け取りは継続しており、財界との関係性を温存している。
川西 立憲は「企業・団体献金全面禁止」「政策活動費の廃止」「政治資金パーティ禁止」を明確に掲げ、抜本改革案を国会に提出。また、政治資金の電子化・即時公開など透明性向上に向けた先進的な提案も行っている。
森岡 共産はさらに一歩踏みこみ、企業献金・政党助成金ともに全面廃止を主張している。実際に同党は企業・団体献金を一切受け取らず、党費と個人献金のみに依拠する運営を貫いている。社民も政党助成金を除けば共産とほぼ同様の立場だ。
川西 改革に本気で取り組もうとする勢力と、既得権に固執する勢力との構図が鮮明になっている。とくに自民党が長年依存してきた企業献金体制と、それを容認した他の保守政党との構造的な癒着は、表面的な法改正では根本解決できない。国民が情報を見極め、選挙において「企業よりも国民を優先する政治」を掲げる候補と政党を選び直すことが決定的に重要だ。これらの腐敗の構造に終止符を打てるかどうか、私たち個人の判断が問われている。
医療・介護が地方を支える社会保障から始まる経済の好循環
武村 医療と介護の充実は、地方における持続可能な発展の基盤を築く重要な柱だ。医療・福祉分野は、単に生活を支えるインフラにとどまらず、地域の雇用創出と経済循環の中核を担っている。森岡 総務省の「経済センサス」や厚生労働省の統計によれば、日本全国の医療・福祉分野の就業者は2023年時点で約880万人に達し、全就業者の1割超を占める。この傾向はとりわけ地方で顕著で、秋田県や高知県などでは全産業のうち医療・福祉部門の就業者が20%前後を占め、農林業や製造業を大きく上回っている。
川西 医療機関や介護施設の存在は、地域に安定した所得をもたらし、周辺の商業・住宅・交通・教育など関連分野への波及効果も大きい。厚労省の試算では、一つの病院がもたらす地域経済への生産波及効果は、病院の売上高の約1.8倍に達するとされている。例えば年間収入が10億円の病院であれば18億円超の経済波及効果を地域にもたらすことになる。
西山 社会保障の充実は住民の家計を安定させ、可処分所得を増やす効果もある。医療・介護費の自己負担軽減は生活不安を和らげ、支出を消費に向けることを可能にする。これにより、需要の下支えと地元産業の活性化が実現し、経済の「下からの押し上げ」が生まれる(図2)。このように、医療と介護の分野は「負担」ではなく、「地域の未来への投資」であり、福祉と経済を両立させる成長戦略の要だ。防衛費や大型公共事業に偏る財政のあり方を見直し、暮らしの安心にこそ税財源を振り向けるべきときだ。医療・介護を支えることこそが、地方を再生し、社会に持続可能な好循環をもたらす確かな道だ。
命と暮らし、そして倫理を守るため投票に行こう
西山 私たち医師・歯科医師は、病める人々に寄り添い、命と健康を守る使命を担い、高い倫理性が求められている。医の倫理とは、単に医療技術を提供することではなく、患者の尊厳を守り、誰もが平等に、安心して医療を受けられる社会を実現することに他ならない。現在、医療現場は重大な岐路に立たされている。物価の高騰と度重なる医療費抑制政策により、多くの医療機関が経営の危機に直面し、患者もまた、保険料や窓口負担の増加、生活の困窮により受診を控える現実がある。こうした事態に沈黙することは、医師としての倫理に反するのではないだろうか。
木原 命と健康を守るという観点からすれば、学問の自由を脅かす学術会議法人化法や戦争放棄を掲げた憲法9条改憲に対する姿勢も重要な争点と感じている。
森岡 エネルギー政策や震災復興も同様だ。政府与党は福島第一原発事故の反省を投げ捨て、新増設を含む原発の活用に舵を切った。能登半島地震被災者は置き去りにされ、医療費窓口負担免除措置の継続も不透明なままだ。
川西 どの党が命を大切にし、社会保障の拡充を真摯に目指しているのか。冷静に見極め、今こそ医療の現場から、私たちの声を届けるときだ。
武村 協会は、命を削る政治に抗し、すべての人が安心して医療を受けられる社会の実現をめざして活動している。医師として、そして一市民として、ぜひ投票に足を運んでいただきたい。
図1 OTC薬に保険が使えなくなると... ※初再診科、各種管理料、処方せん料等を除く
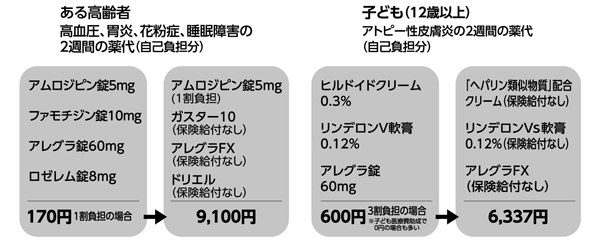
図2 社会保障の充実が経済の好循環につながる