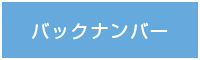2025年8月05日(2109号) ピックアップニュース
特別インタビュー ABC for Peace(いっぽプロジェクト)
核なき未来へ"いっぽ"を踏み出す若手医療者たち 次世代への架け橋に


2023年に北海道で開かれた「反核医師のつどい」で結成!
若手がつながり「アクション」できる場に
稲原 2023年6月に東京で行われた反核医師の会の全国大会で、たまたま長野県の松本協立病院で働く医師の光武鮎さんの隣の席になりました。その時に、光武さんから「反核医師の会の後継者となる若手が活動できるプロジェクトを立ち上げたい」と話があり、「じゃあ一緒にやりませんか」と声をかけたのが、きっかけでした。
実際の結成はその年の9月に行われた「第33回反核医師のつどいin北海道」の時でした。それまでに月1回くらい5~6人で集まり準備を進め、「つどい」の日には、全国から医学生や若手の医療従事者30人弱が集まりました。グループディスカッションで「どういうことがしたいのか」「なぜこういう活動に関わることになったのか」などをみんなで話し、懇親会の二次会でも話し合って、最終的に「つどい」の最後に投票で決めたプロジェックト名を発表し、活動をスタートしました(上写真)。

河野絵理子さん(医師、長野中央病院・埼玉県川口診療所)

丸橋 郁弥さん(介護福祉士、長野県)

荒木さくらさん(医師、熊本県・くわみず病院)
河野 この「ABC」に思いが込められていて、Aはアクション、Bはブリッジ、Cはヘルスケアワーカーの「ケア」です。
学生の時から反核医師の会の学生部会や「つどい」に参加していて、すごく勉強になるのですが、先輩の先生たちのとても高度なディスカッションを、受け身で聞くだけになってしまっていて、ちょっとモヤモヤしていました。私たち自身も行動したいという思いがあったので、アクション=行動するための主体になろうという思いでつくったというのが一つです。
ブリッジはいろんな世代、地域を超えてつながるということ、何よりも、世界中で核廃絶の運動が盛り上がっているので、国境も超えるという意味を込めました。
最後の「ケア」は、「反核医師の会」は基本的には医師と歯科医師の運動なのですが、多職種の仲間がたくさんいるので、プロジェクトでは職種も超えて活動できるようにという意味で、ヘルスケアワーカーの「C」を取りました。
次世代継承考えるワークショップなど開催
口分田 これまでの取り組みについて教えてください。丸橋 大きな活動として、核兵器禁止条約の締約国会議への参加と、反核医師のつどいでの企画があります。
また、メンバーの思いや社会情勢などに応じて、企画を検討してきました。2023年にはパレスチナ・ガザの問題で、北海道パレスチナ医療奉仕団団長の猫塚義夫先生をお招きして学習会をしたり、政府に核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める動画リレーも行いました。動画リレーは、全国の医療機関で働く医療者たちからメッセージを集め、SNS(フェイスブックやユーチューブ、Xなど)でアピールしていくという取り組みです。
去年の「つどい」は沖縄で開催ということもあり、沖縄陸軍病院20号壕群を見学しました。医療者が戦争にどう加担してしまったのか、またはどういう役割を押し付けられてしまったのかという視点から歴史を学ぶ良い機会になったのかなと思っています。
河野 被団協代表委員の田中熙巳さんらが呼びかけ、今年2月に開催された「被爆80年 核兵器をなくす国際市民フォーラム」では「Bridge!~医療・法律・教育をつないで次世代継承を考えよう~」というワークショップを企画しました。
医療・法律・教育に関わる20~30代のメンバーがそれぞれの専門性を活かした日々の活動の交流や核廃絶への思い、視点を共有し、核廃絶の必要性や今後の展望について深めるとともに、運動の世代継承や次世代への運動のあり方なども議論しました。
その準備段階で、「反核医師の会の歴史を私たちはあまり知らないのではないか」という話になり、代表世話人の中川武夫先生をお呼びして会の歴史を学ぶ企画を行いました。この企画で、先輩たちから学ぶことがすごくたくさんあると気づき、今年の「第35回反核医師のつどいin東京」のテーマが「継承」なので、先輩の話を聞く機会をプロジェクトとして持とうと、5~7月に3回にわたってプレ企画を実施しました。
1回目は聞間元先生にお話を伺いました。先生は第五福竜丸が帰港した焼津港のある静岡県の医師で、ビキニ環礁のマーシャル諸島で被爆者の健診などをされてきました。
2回目は、長年被爆者の相談支援活動に取り組んでこられた広島原爆被害者相談員の会代表の三宅文枝さんに話をうかがいました。
3回目は、青木克明先生から在外被爆者の支援に関わられたこと、そして先生ご自身が被爆二世であることなどをお聞きしました。

稲原 真一さん(事務職 東京都)

インタビュアー
口分田 真 副理事長
核兵器禁止条約の国際会議にも参加
河野 私が参加したのは2023年の第2回締約国会議だったんですが、国際会議への参加自体が初めてで、すごくドキドキしました。核兵器禁止条約の締約国会議は、市民が参加できるという点で、国際会議としてはまれなものだったみたいです。
印象的だったのは、会場に1階席と2階席があって、1階席に各国の代表の方とともに、発言する市民団体の代表の方がいたことです。市民団体も各国の代表も同じフラットな場所にいて、私たちのような一参加者の市民は2階席にいるのですが、ドリンクなどを持ち込んで、皆さん自由に聞くことができました。2階席から1階席への出入りのハードルも全然なく、私も知り合いの方が発言されるので、その写真を撮りに1階に降りると、すごく近い場所で撮れるという感じでした。国際会議がこんなに自由なんだということ、市民の発言が会議の議事録に残り、今後国際的に重要視されるんだということを、一市民として実感できました。
国際的な核廃絶の議論に関われるんだと身に染みて感じられたことがとても楽しく、重要な経験をさせてもらったなというのが一番思っていることです。
荒木 私は今年3月に、第3回の締約国会議に参加させてもらいました。日本の若者がいろいろな市民団体から多数参加しており、核問題をジェンダーの視点で考える取り組みをされている団体の方などが、本会議で発言されていました。
日本政府は条約の批准どころか、締約国会議へのオブザーバー参加すらせず、ジェンダーの問題でも世界から遅れをとっている中、日本にも、そういう問題に取り組んでいる若者がいて、その人たちの研究や発言、提言が盛り込まれるというのはすごいことで、被爆者の方々はもちろんのこと、日本の市民が核廃絶をリードしている部分があると感じました。
今回の第3回締約国会議では、核兵器を安全保障上のリスクとして捉え、そのリスクを研究・追求していくことがテーマになりました。
核保有国は「自国の安全保障を守るためで、実際の使用は想定していない」と主張しますが、結局核兵器を持っていることで、脅威を感じた他の国も核兵器を手放せなくなったり、AIの導入など新たなシステムエラーや人の判断ミスによる誤爆のリスクが、核兵器が存在する限り消せないという話がありました。先日のアメリカによるイランの核施設攻撃を見ても、結局、核兵器が火種になって争いが起きているのではないかと改めて思いました。

2025年IPPNW(核戦争防止国際医師会議)のユースの企画で。中央が荒木さん
1985年にノーベル平和賞を受賞した核戦争防止国際医師会議(IPPNW)のユースの企画にも参加でき(右写真)、世界にも核廃絶運動をしている医学生や医師がいるのだと勇気づけられました。国内だけで活動していると孤独感や「なかなか広がらないな」という感覚があったりするのですが、今回の参加がそれを払しょくしてくれました。
核廃絶にかかわるきっかけ
口分田 今、皆さんがされていることは本当にすごいことと思うんです。私は皆さんの年齢の頃、初期研修や大学院在学中は研究、アルバイトに明け暮れて、社会的なことに何も目を向けることができていませんでした。活動をしようというきっかけは何だったのでしょうか。河野 中学生の時に家族旅行で広島の平和記念資料館に連れて行ってもらい、その時初めて原爆投下という事実を知りました。被爆者が描いた絵がたくさん飾られていて、それが本当に衝撃的で頭から離れなかったことが、一番の体験だなと思います。
その後、高校生になり、両親が医療関係者だったこともあって、あまり深く考えずに医学部を受験の選択肢として考えていました。ただ、「医師という社会的責任のある立場に、自分がなれるのだろうか」という自信のなさがずっとありました。ニュースで日本でも世界でも飢餓や貧困で苦しんでいる人がいるという映像を目にし、自分が何もできていないこと、そもそも知らないことが多いということに、自信を失っていました。
そんな自信のなさを抱えたまま医学部に入学してしまった時に出会ったのが、反核医師の会でした。先ほど話に出てきた光武鮎さんが信州大学の先輩で、反核医師の会の学生部会や「つどい」に誘ってもらいました。医者という立場で、臨床をしながら平和な社会のために実際に行動している先輩方の存在に衝撃を受けました。「エゴかもしれないけれど、何もできないという感覚を覆せるのではないか」「私にもできる行動があるんだ」と思えたことが、今も活動を続けている理由なのだと思います。
荒木 私は大学に入って社会問題について考えるようになり、サークルでそうした社会活動をすることが楽しかったのですが、就職してから、そういう機会がなくなってしまいました。
昔と違い今、「働き方改革」で研修医は「早く帰れ」と言われるため時間があって、そんな時に北海道の「つどい」の情報が来て参加したんです。その「つどい」がちょうど「いっぽプロジェクト」の立ち上げでした。同世代で一緒にできる場というのがよかったと思います。一人ではなかなか続かないけれど、一緒にやれる人がいるといいなと思うんです。
口分田 思いが近い人間の中では、共通認識があって、いろんな話ができると思うんです。ただ、核抑止力が必要だという人や「あなたたちは本当に核廃絶ができると思っているの?」などと言われる方々が、悲しいことに医師の中にもおられます。そういう方々との対話も深めていかないといけないと思いますが。
丸橋 後輩の職員たちから「世界って変われるの?」「無理だよね」という消極的な声を聞くことがあります。そういった時に話すのは「本当に世界って変わってないのかな?」ということです。
私は介護士をしていましたが、数十年前は「認知症」という言葉自体がなかったと思うんです。認知症が理解され、治療やケアにつながるようになったのは、ここ数十年のことです。先ほど話があった「残業するな」も、昭和の時代には本当に考えられなかったと思うんです。世界は変わっています。確かに悪くなっている部分もありますが、よくなってきた部分もたくさんあるじゃないか、という話を後輩たちにしています。
核兵器に関して、10年前だったら私もかなり弱気になっていたと思いますが、「核兵器禁止条約」ができて、世界各国、大国以外の多数の国々が批准して、世界が核兵器廃絶に向けて動いている。5~6年前には考えられなかった状況です。
全国の仲間を増やし被爆者医療の継承へ
口分田 最後に、いっぽプロジェクトの今後の目標と、兵庫の医師・歯科医師へのメッセージをそれぞれお願いします。稲原 もっと仲間を増やしたいということが一番の目標です。思いはあるけれど一人でモヤモヤとしている人たちが全国にいると思っていて、そういう人たちとつながって活動できる場にできたらと思っています。
荒木 本当に「仲間を増やしたいなあ」という思いが、強いです。特に熊本で一緒に活動する仲間をもっと増やしたいなと思いますね。
みんなが平和のことを考える時間が少しでも増える、それだけでとても意味があると感じています。核兵器禁止条約について、正直、国内の報道が少なく、「締約国会議に参加した人がいるらしいよ」と話題づくりができて少しでも認知度を高めていけたらと思っています。
丸橋 今、6歳の息子がおり、自分自身が家族に継承していくということが大事だと思っています。継承できるように、学びを深めて学習し、行動していくことが大きな目標と思います。
身近な目標は、私のいる病院でいっぽプロジェクトに関わってくれる人を作ることです。兵庫県の先生方とも交流できたらと思います。
河野 私は、「被爆者医療の継承」が、いっぽプロジェクトの使命の一つでもあるのかなと、最近感じています。これまでの取り組みを通じて、反核医師の会のたくさんの先輩方が被爆者の方々に寄り添い、人生を共に生きてきたと知りました。先輩方がどんな思いでやってこられたのか、それがどのように核廃絶に向けた運動になってきたのか、改めて私たちが継承し、橋渡しとして引き継いでいきたいというのが、大事な目標だと思っています。
兵庫県保険医協会の皆さんといえば、やはり中心になって行っているDBOB(Don't Bank on the Bomb,核兵器にお金を貸すな)キャンペーン(下)が本当にすごいと思います。歌とアニメーションがとても好きで、歌の最後に「いっぽ」という言葉を入れてくださって、私たちのプロジェクトにつながるのも本当にうれしかったです。何よりも、締約国会議でも再三にわたり指摘されている、核兵器製造企業への投資と融資は核関連行為への援助に当たるという、非常に大切な部分にアプローチしていくという実行力を持つ内容で、その発想力や実行力を教えてもらいたいなと思っています。
口分田 引き続き、核兵器のない社会を目指して、交流をしながら、お互い頑張っていきましょう。今日はどうもありがとうございました。