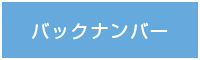2025年8月25日(2110号) ピックアップニュース
[談話] 参議院選挙の結果について
自公政治への厳しい審判 診療報酬増と「消費税減税」実現を
兵庫県保険医協会 政策・運動・広報委員会
2025年7月に実施された参議院選挙は、長年続いてきた自公政権の政治姿勢と政策に対する国民の不信と怒りが示された重要な転機であった。自民・公明の与党が参議院で過半数を割った結果は、政権が進めてきた政治に対する厳しい審判である。
第一に、物価高騰や社会保障の切り捨てが進むなか、消費税減税など国民の生活に向き合う誠実な政策はほとんど見られず、困窮と格差が拡大している。第二に、外交・経済政策において、日本政府は対米追従の姿勢を改めず、トランプ米大統領による日本製品への関税交渉においても、何ら有効な対抗軸や外交的交渉戦略を示せていない。これは経済主権の喪失に等しく、国民経済を脅かす深刻な事態である。第三に、裏金問題など、自民党の金権体質は、政治に対する信頼を著しく損なってきた。
こうした不満は、与党の後退だけでなく、参政党を含む非既成政党の伸長というかたちでも現れた。参政党が展開する排外主義的・差別的な主張は、フェイクニュースや不安煽動を基盤とし、民主主義を揺るがす危険性を孕んでいる。さらに深刻なのは、こうした極端な主張に、自民党、維新の会、国民民主党などの既成政党までもが引っ張られ、その主張を部分的に取り入れることで、全体として政治の右傾化と劣化が進む可能性をはらんでいる点である。
医療や社会保障といった公共政策の分野でも、人権や公平性の観点よりも、感情的・排他的な論理が幅を利かせ始めていることを、私たちは強く懸念している。
なかでも、維新の会や国民民主党が主張する「社会保険料の引き下げ」は、国民皆保険制度の維持可能性を危うくするだけでなく、若者と高齢者の対立を煽るかたちで世代間分断を生み出すものである。これは、社会保障の本来の趣旨に反するものであり、日本社会の統合を脅かす極めて問題のある主張である。医療・介護現場では、慢性的な人材不足と診療報酬の抑制が続いており、さらなる低医療費政策は制度崩壊に直結しかねない。
もっとも、今回の選挙戦において、医療や社会保障の充実か、それとも軍事費の拡大・軍拡かという国家の根本的なあり方を問う重大な争点が、十分に国民的な議論となり得なかったことは、きわめて残念である。物価高や生活不安が広がるなかでこそ、限られた財源をどこにどう配分するかという問題は、本来、民主主義の根幹にかかわる重要な論点であるべきであった。しかし、防衛予算の増大が既定路線とされる一方で、医療や社会保障への公的支出を抑制し続ける政策の是非が、正面から問われる機会は乏しかった。こうした状況を踏まえ、今後は国民的な議論の深化が求められる。
一方で、今回の選挙で肯定的に評価すべき点もある。政治不信が広がるなか、投票率が前回を上回り、主権者としての自覚が広がりつつあることは、民主主義の健全な再構築に向けた重要な一歩である。また、医療費抑制政策に反対する立憲民主党、日本共産党、社民党などによる野党共闘が17選挙区で候補者を一本化し、一定の成果を上げたことは、今後の政治的選択肢の形成に向けた希望ある前進といえる。
特筆すべきは、野党が一貫して掲げた「消費税減税」が国民の強い支持を得たことである。これは生活支援にとどまらず、医療機関が長年苦しんできた「控除対象外消費税」の問題を解決する糸口でもある。現在、医療機関は診療報酬で消費税分を十分に補填されておらず、実質的な負担を強いられている。消費税減税の実現は、こうした不公平を是正し、地域医療の持続可能性を高める上で極めて重要な施策である。
私たちは、引き続き、すべての人の命と健康を守る医療制度の確立を目指し、現場からの政策提言と運動を粘り強く続けていく決意である。あわせて、医療をはじめとする社会保障の充実は、人々の安心と生活を支えるだけでなく、可処分所得の向上や雇用の拡大を通じて内需を支え、経済の好循環を生み出す力ともなる。こうした視点に立ち、持続可能な経済社会の構築にも貢献することを重視しながら、今後の取り組みを進めていく。
第一に、物価高騰や社会保障の切り捨てが進むなか、消費税減税など国民の生活に向き合う誠実な政策はほとんど見られず、困窮と格差が拡大している。第二に、外交・経済政策において、日本政府は対米追従の姿勢を改めず、トランプ米大統領による日本製品への関税交渉においても、何ら有効な対抗軸や外交的交渉戦略を示せていない。これは経済主権の喪失に等しく、国民経済を脅かす深刻な事態である。第三に、裏金問題など、自民党の金権体質は、政治に対する信頼を著しく損なってきた。
こうした不満は、与党の後退だけでなく、参政党を含む非既成政党の伸長というかたちでも現れた。参政党が展開する排外主義的・差別的な主張は、フェイクニュースや不安煽動を基盤とし、民主主義を揺るがす危険性を孕んでいる。さらに深刻なのは、こうした極端な主張に、自民党、維新の会、国民民主党などの既成政党までもが引っ張られ、その主張を部分的に取り入れることで、全体として政治の右傾化と劣化が進む可能性をはらんでいる点である。
医療や社会保障といった公共政策の分野でも、人権や公平性の観点よりも、感情的・排他的な論理が幅を利かせ始めていることを、私たちは強く懸念している。
なかでも、維新の会や国民民主党が主張する「社会保険料の引き下げ」は、国民皆保険制度の維持可能性を危うくするだけでなく、若者と高齢者の対立を煽るかたちで世代間分断を生み出すものである。これは、社会保障の本来の趣旨に反するものであり、日本社会の統合を脅かす極めて問題のある主張である。医療・介護現場では、慢性的な人材不足と診療報酬の抑制が続いており、さらなる低医療費政策は制度崩壊に直結しかねない。
もっとも、今回の選挙戦において、医療や社会保障の充実か、それとも軍事費の拡大・軍拡かという国家の根本的なあり方を問う重大な争点が、十分に国民的な議論となり得なかったことは、きわめて残念である。物価高や生活不安が広がるなかでこそ、限られた財源をどこにどう配分するかという問題は、本来、民主主義の根幹にかかわる重要な論点であるべきであった。しかし、防衛予算の増大が既定路線とされる一方で、医療や社会保障への公的支出を抑制し続ける政策の是非が、正面から問われる機会は乏しかった。こうした状況を踏まえ、今後は国民的な議論の深化が求められる。
一方で、今回の選挙で肯定的に評価すべき点もある。政治不信が広がるなか、投票率が前回を上回り、主権者としての自覚が広がりつつあることは、民主主義の健全な再構築に向けた重要な一歩である。また、医療費抑制政策に反対する立憲民主党、日本共産党、社民党などによる野党共闘が17選挙区で候補者を一本化し、一定の成果を上げたことは、今後の政治的選択肢の形成に向けた希望ある前進といえる。
特筆すべきは、野党が一貫して掲げた「消費税減税」が国民の強い支持を得たことである。これは生活支援にとどまらず、医療機関が長年苦しんできた「控除対象外消費税」の問題を解決する糸口でもある。現在、医療機関は診療報酬で消費税分を十分に補填されておらず、実質的な負担を強いられている。消費税減税の実現は、こうした不公平を是正し、地域医療の持続可能性を高める上で極めて重要な施策である。
私たちは、引き続き、すべての人の命と健康を守る医療制度の確立を目指し、現場からの政策提言と運動を粘り強く続けていく決意である。あわせて、医療をはじめとする社会保障の充実は、人々の安心と生活を支えるだけでなく、可処分所得の向上や雇用の拡大を通じて内需を支え、経済の好循環を生み出す力ともなる。こうした視点に立ち、持続可能な経済社会の構築にも貢献することを重視しながら、今後の取り組みを進めていく。