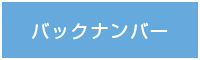2025年8月25日(2110号) ピックアップニュース
主張 戦後80年 記憶の継承にむけて
今年は戦後・被爆80年にあたる年となる。
先の戦争はすでに「記憶」から「歴史」へ変わりつつある、とはよく言われるが、80年といえば、ほぼ人の一生に相当する年月であり、確かに当時の戦争を実際の体験として記憶し語れる方々は、どれだけ若く見積もっても、80代後半以上の年代となっている。
先日の日本世論調査会の報告でも、日中戦争と太平洋戦争を「戦争体験を含め直接知っている」と答えた人はわずか3%に留まり、戦争体験者の記憶の新たな継承は年々困難になりつつある現状がある。
その一方、希望を見出すことのできる調査結果もある。日本財団が戦後80年をテーマに行った「18歳意識調査」では、全体の95%が太平洋戦争に関する学習経験があると答え、印象に残った学習内容に関しては3人に2人が「学校での授業の内容」を挙げたとのこと。また、戦争を題材にした記憶に残る書籍や映画では、「火垂るの墓」が40%を超えトップに、「はだしのゲン」がそれに次いだとの結果だった。
これからの日本が目指すべき国づくりについての質問(重複回答)には、2位の「経済に強い国」、3位の「災害に強い国」を抑え、4割以上の回答者が「自由で平和な国」をあげ1位となった。戦後80年の平和教育の成果が、今でも根強く認められる結果ではないだろうか。
会員の多くも、子ども時代から現在に至るまで、様々な書籍や映像などで、先の戦争が招いた数々の悲劇を知ったのではないだろうか。その中には、戦争経験者自身が残したものもあれば、戦争の記憶を受け継いだ戦後世代の手によるものもあっただろう。
それらを通じて語られる戦争は、悲しみや怒り、怯え、恐れ、悼みの感情とともに、戦争をしていない時代に生きていることのありがたさ・尊さを、改めて実感させる機会となってきた。
おりしも昨年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞した。被爆者の声、そして戦争体験者の声を、日本国内のみならず世界中へ届ける良い機会となったことも事実であるが、それと共に、今こそ被爆者・戦争体験者から戦禍の悲痛な記憶を継承したわれわれ一人ひとりが共に当事者となり、平和への声をあげ続けることが、より一層大切になっている。
広島にある原爆慰霊碑に刻まれる、「過ちは繰り返しませぬから」の文字。
戦争の記憶を引き継いだ、現在を生きるわれわれこそが、この言葉の「主語」を、未来永劫にわたり引き受けねばなるまい。
先の戦争はすでに「記憶」から「歴史」へ変わりつつある、とはよく言われるが、80年といえば、ほぼ人の一生に相当する年月であり、確かに当時の戦争を実際の体験として記憶し語れる方々は、どれだけ若く見積もっても、80代後半以上の年代となっている。
先日の日本世論調査会の報告でも、日中戦争と太平洋戦争を「戦争体験を含め直接知っている」と答えた人はわずか3%に留まり、戦争体験者の記憶の新たな継承は年々困難になりつつある現状がある。
その一方、希望を見出すことのできる調査結果もある。日本財団が戦後80年をテーマに行った「18歳意識調査」では、全体の95%が太平洋戦争に関する学習経験があると答え、印象に残った学習内容に関しては3人に2人が「学校での授業の内容」を挙げたとのこと。また、戦争を題材にした記憶に残る書籍や映画では、「火垂るの墓」が40%を超えトップに、「はだしのゲン」がそれに次いだとの結果だった。
これからの日本が目指すべき国づくりについての質問(重複回答)には、2位の「経済に強い国」、3位の「災害に強い国」を抑え、4割以上の回答者が「自由で平和な国」をあげ1位となった。戦後80年の平和教育の成果が、今でも根強く認められる結果ではないだろうか。
会員の多くも、子ども時代から現在に至るまで、様々な書籍や映像などで、先の戦争が招いた数々の悲劇を知ったのではないだろうか。その中には、戦争経験者自身が残したものもあれば、戦争の記憶を受け継いだ戦後世代の手によるものもあっただろう。
それらを通じて語られる戦争は、悲しみや怒り、怯え、恐れ、悼みの感情とともに、戦争をしていない時代に生きていることのありがたさ・尊さを、改めて実感させる機会となってきた。
おりしも昨年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞した。被爆者の声、そして戦争体験者の声を、日本国内のみならず世界中へ届ける良い機会となったことも事実であるが、それと共に、今こそ被爆者・戦争体験者から戦禍の悲痛な記憶を継承したわれわれ一人ひとりが共に当事者となり、平和への声をあげ続けることが、より一層大切になっている。
広島にある原爆慰霊碑に刻まれる、「過ちは繰り返しませぬから」の文字。
戦争の記憶を引き継いだ、現在を生きるわれわれこそが、この言葉の「主語」を、未来永劫にわたり引き受けねばなるまい。