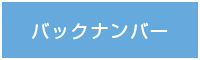2025年10月15日(2115号) ピックアップニュース
特集 神戸市長選挙 政策解説㊤
神戸市医療提供体制の危機と再生への課題
10月12日告示・26日投開票で行われる神戸市長選挙にあたり、市政課題を2回に分けて解説する。初回は市内の医療提供体制についてを取り上げる。
保団連の調査では、2024年1月と比較して66%の医療機関が「収入が減少」と回答し、92%が「診療報酬ではコスト上昇を補填できない」としている。賃上げを実施した医療機関の9割が「賃上げ分をカバーできない」と答えており、医療現場の切迫した状況が浮き彫りになっている。
神戸市内でも、24年度に中央市民病院が31.1億円、西市民病院が8.1億円、西神戸医療センターが11.8億円の経常赤字を計上しており、公的医療機関でさえ持続的運営が危ぶまれている。
こうした事態を受け、自治体でも支援策が始まっている。東京都は2025年度予算案で総額321億円の「地域医療確保緊急支援事業」を行い、大阪市や仙台市も独自の財政措置を実行している。
神戸市も地域医療を守るため、こうした施策を早急に検討すべきである。
特に小児・周産期・救急医療やかかりつけ医の継続的維持、職員の確保・処遇改善に向けた経済支援が不可欠であり、患者負担を抑えつつ医療機関を下支えする仕組みの構築が求められる。
小児の急病は状態が急変しやすく、早期の入院治療が必要な場合も多い。にもかかわらず、地域によって入院先が限られている現状は、市民の安心を損なう重大な課題である。
市内全域で子どもたちが必要な医療を受けられる体制を整備し、特に灘区・兵庫区・垂水区など医療空白地域での病床確保を急ぐ必要がある。
あわせて、小児科医の確保や看護師体制の強化、救急搬送ネットワークの充実を図ることで、地域全体の小児救急医療の質を高めることができる。これにより、家庭や地域での育児支援と一体となった「安心して子育てできるまちづくり」を進めることが可能となる。
神戸市は、こうした地域偏在を解消し、子どもの命を守る医療提供体制の再構築に早急に取り組む必要がある。
主な論点は、新病院の立地、運営体制、人材確保、財政の健全化、地域医療への影響、そして未払い残業代問題への対応である。
新病院は両病院の中間にあたる神戸市北区長尾町宅原に建設予定だが、公共交通の便や道路事情などアクセス面での課題が指摘されている。運営体制についても、統合後の方針や医師・看護師などの人材確保、既存職員の処遇の保障などが懸念されており、地域医療の質を維持するための丁寧な対応が求められる。
財政面では、赤字経営が続いた済生会兵庫県病院の再建が統合によって実現するのか、新病院が持続的に運営できるのかが焦点である。経営の透明性と効率性の確保が不可欠である。
また、通院距離の増加や救急搬送時間の延伸など、高齢者や交通弱者への負担増も懸念される。これら生活に直結する問題に対しては、十分な対策が必要である。
さらに、三田市民病院の過去の未払い残業代問題を教訓とし、労務管理体制を整え、職員が安心して働ける環境を構築することが重要である。
市は地域住民への丁寧な説明と意見聴取を重ね、地域医療の後退を招かないよう段階的かつ慎重に統合計画を進めるべきである。
市は有識者による「病床機能検討部会」を設置して改善状況を監視し、徳洲会側も改善計画書を提出した。改善期限は2024年8月末であり、その結果を踏まえて今月10月6日に神戸市は同病院の「医療安全管理体制は確立された」と判断、医療監視を年2~3回に増やすなど、引き続き指導・助言をしていく、と発表した。新病院開設の可否は今後、判断される見通しである。
新病院は垂水区旭が丘2丁目の旧垂水体育館・養護学校跡地に建設予定だったが、開設は少なくとも2026年以降にずれ込む見込みである。
垂水区はもともと医療体制が脆弱で、人口当たりの病床数が市内で最も少ない。特に産科・小児科の病床不足が深刻であり、掖済会病院が2016年度に相次いで産婦人科・小児科を閉鎖して以来、地域医療の空白が続いてきた。 徳洲会病院は2021年に産婦人科病床を設置したが、小児科病床は依然として不足している。15歳以下人口や出生数が多い垂水区にとって、産科・小児科を備えた新病院の早期開設は喫緊の課題である。
市は引き続き、同病院の医療安全管理体制を指導すること、徳洲会も市の指導の下で体制改善に取り組み、地域医療を支える役割を果たすことが求められている。
移転後の医療提供体制やアクセスの利便性、地域医療への影響について多くの課題が指摘されている。灘区は急性期病院が少なく、高齢化によって医療需要が増している地域であり、六甲病院が果たす役割は大きい。そのため、移転によって灘区の患者が通院しづらくなる懸念がある。
移転計画は、灘区・東灘区双方の地域医療の持続性を確保する観点から慎重に検討する必要がある。
神戸市は、病院運営法人と緊密に連携し、この移転が地域医療の充実に資するよう指導・助言を行うべきである。
住民や医療関係者との十分な対話を重ね、両区にとって有益な医療体制の整備を目指すことが重要である。
神戸市長選では、少子高齢化と物価高騰の中で、神戸市が市民の命と暮らしを守る自治体としての責務を果たせるのかが問われている。
医療機関経営に対する抜本的な支援を
全国の医療機関では、物価や人件費の高騰が続く一方、診療報酬の抑制が長期化し、経営が極めて厳しい状況にある。保団連の調査では、2024年1月と比較して66%の医療機関が「収入が減少」と回答し、92%が「診療報酬ではコスト上昇を補填できない」としている。賃上げを実施した医療機関の9割が「賃上げ分をカバーできない」と答えており、医療現場の切迫した状況が浮き彫りになっている。
神戸市内でも、24年度に中央市民病院が31.1億円、西市民病院が8.1億円、西神戸医療センターが11.8億円の経常赤字を計上しており、公的医療機関でさえ持続的運営が危ぶまれている。
こうした事態を受け、自治体でも支援策が始まっている。東京都は2025年度予算案で総額321億円の「地域医療確保緊急支援事業」を行い、大阪市や仙台市も独自の財政措置を実行している。
神戸市も地域医療を守るため、こうした施策を早急に検討すべきである。
特に小児・周産期・救急医療やかかりつけ医の継続的維持、職員の確保・処遇改善に向けた経済支援が不可欠であり、患者負担を抑えつつ医療機関を下支えする仕組みの構築が求められる。
小児救急体制の充実を
神戸市内で小児の入院が可能な病院(小児入院医療管理料届出医療機関)は12カ所に限られており、県立こども病院や中央市民病院など、中心部に偏在している。灘区、兵庫区、垂水区には小児入院施設がなく、急病時には遠方への搬送を余儀なくされ、医療の初動対応が遅れるおそれがある。小児の急病は状態が急変しやすく、早期の入院治療が必要な場合も多い。にもかかわらず、地域によって入院先が限られている現状は、市民の安心を損なう重大な課題である。
市内全域で子どもたちが必要な医療を受けられる体制を整備し、特に灘区・兵庫区・垂水区など医療空白地域での病床確保を急ぐ必要がある。
あわせて、小児科医の確保や看護師体制の強化、救急搬送ネットワークの充実を図ることで、地域全体の小児救急医療の質を高めることができる。これにより、家庭や地域での育児支援と一体となった「安心して子育てできるまちづくり」を進めることが可能となる。
神戸市は、こうした地域偏在を解消し、子どもの命を守る医療提供体制の再構築に早急に取り組む必要がある。
済生会兵庫県病院と三田市民病院統合をめぐる課題
済生会兵庫県病院と三田市民病院の統合には多くの課題があり、市民の間にも不安が広がっている。主な論点は、新病院の立地、運営体制、人材確保、財政の健全化、地域医療への影響、そして未払い残業代問題への対応である。
新病院は両病院の中間にあたる神戸市北区長尾町宅原に建設予定だが、公共交通の便や道路事情などアクセス面での課題が指摘されている。運営体制についても、統合後の方針や医師・看護師などの人材確保、既存職員の処遇の保障などが懸念されており、地域医療の質を維持するための丁寧な対応が求められる。
財政面では、赤字経営が続いた済生会兵庫県病院の再建が統合によって実現するのか、新病院が持続的に運営できるのかが焦点である。経営の透明性と効率性の確保が不可欠である。
また、通院距離の増加や救急搬送時間の延伸など、高齢者や交通弱者への負担増も懸念される。これら生活に直結する問題に対しては、十分な対策が必要である。
さらに、三田市民病院の過去の未払い残業代問題を教訓とし、労務管理体制を整え、職員が安心して働ける環境を構築することが重要である。
市は地域住民への丁寧な説明と意見聴取を重ね、地域医療の後退を招かないよう段階的かつ慎重に統合計画を進めるべきである。
神戸徳洲会病院の新病院計画と課題
垂水区の神戸徳洲会病院は、今年2月の新病院開設を予定していたが、医療安全管理体制の不備が相次ぎ、計画は大幅に遅延している。カテーテル治療後の死亡事例やインスリン投与の不適切事例などが発覚し、神戸市は2024年2月、医療法に基づき運営法人・徳洲会に改善命令を出した。市は有識者による「病床機能検討部会」を設置して改善状況を監視し、徳洲会側も改善計画書を提出した。改善期限は2024年8月末であり、その結果を踏まえて今月10月6日に神戸市は同病院の「医療安全管理体制は確立された」と判断、医療監視を年2~3回に増やすなど、引き続き指導・助言をしていく、と発表した。新病院開設の可否は今後、判断される見通しである。
新病院は垂水区旭が丘2丁目の旧垂水体育館・養護学校跡地に建設予定だったが、開設は少なくとも2026年以降にずれ込む見込みである。
垂水区はもともと医療体制が脆弱で、人口当たりの病床数が市内で最も少ない。特に産科・小児科の病床不足が深刻であり、掖済会病院が2016年度に相次いで産婦人科・小児科を閉鎖して以来、地域医療の空白が続いてきた。 徳洲会病院は2021年に産婦人科病床を設置したが、小児科病床は依然として不足している。15歳以下人口や出生数が多い垂水区にとって、産科・小児科を備えた新病院の早期開設は喫緊の課題である。
市は引き続き、同病院の医療安全管理体制を指導すること、徳洲会も市の指導の下で体制改善に取り組み、地域医療を支える役割を果たすことが求められている。
六甲病院の移転問題と地域医療の課題
六甲病院は、かつて国家公務員共済組合連合会が運営していたが、2021年7月に医療法人若葉会グループが継承し、新体制で診療を続けている。現在は灘区土山町にあるが、JR甲南山手駅周辺(東灘区)への移転計画が進められており、地域住民や医療関係者の関心が高い。移転後の医療提供体制やアクセスの利便性、地域医療への影響について多くの課題が指摘されている。灘区は急性期病院が少なく、高齢化によって医療需要が増している地域であり、六甲病院が果たす役割は大きい。そのため、移転によって灘区の患者が通院しづらくなる懸念がある。
移転計画は、灘区・東灘区双方の地域医療の持続性を確保する観点から慎重に検討する必要がある。
神戸市は、病院運営法人と緊密に連携し、この移転が地域医療の充実に資するよう指導・助言を行うべきである。
住民や医療関係者との十分な対話を重ね、両区にとって有益な医療体制の整備を目指すことが重要である。
市民の命と暮らし守る神戸市政へ
神戸市は全国有数の政令指定都市でありながら、現市政は三宮再開発や空港国際化に多額の予算を投じ、郊外や人口減少地域の医療・福祉・交通など生活インフラを軽視している。公約だった「中学生以下の医療費無料化」も実現せず、国保料の独自控除や法定外繰入を廃止するなど、国の制度改悪に追随する姿勢が目立つ。神戸市長選では、少子高齢化と物価高騰の中で、神戸市が市民の命と暮らしを守る自治体としての責務を果たせるのかが問われている。