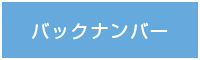2025年11月05日(2117号) ピックアップニュース
近藤克則千葉大学名誉教授が講演
第34回日常診療経験交流会 多職種が活発に交流 格差縮小「保険医の役割大きい」


エトキ 所得と要介護認定や認知症発症との関連を指摘し、医療者としての介入の必要性を指摘した近藤先生(上)
分科会は午前中に3会場で開催。医師・歯科医師のほか、薬剤師や歯科技工士、訪問看護師、理学療法士など多職種から18人が20演題を発表した。
「CKD重症化予防を目指した地域医療連携の取り組み」「日常診療における抗認知症薬レカネマブの使用経験」など連携の取り組みや症例報告のほか、メインテーマ「ネット社会の危うさと医療のかかわり」との関係では、「社会情報医療情報の入手経路」や「医療DXと薬局」などの演題が出され、活発な意見交換がなされた。
他にも、「PFAS運動の取り組み」や「日常診療で役立つ『やさしい日本語』」「被爆80年『Don't Bank on the Bomb』」など、多彩なテーマで報告が行われた。
特別講演に立った近藤先生は2000年頃に過去の話と思われていた「健康格差」を「再発見」したが、再現性やメカニズム、対策など、数々の批判が寄せられたため、神戸市など多くの自治体の協力を得て、その実証研究を行ってきた。
生活習慣の改善ばかりが言われるが、健康を損なう背景には環境・社会的要因があるという認識が重要であり、国内でもWHOの総会決議に盛り込まれたことをきっかけに、医師会や厚労省も健康格差とその改善の重要性を徐々に認識するようになり、取り組みが進みつつあるとした。
そして、健康格差縮小のための「ゼロ次予防」の取り組みのヒントは地域コミュニティへの参加にあり、臨床に加え、コミュニティづくり・社会保障制度を守る運動などの重層的・多面的介入で健康格差の小さい社会づくりは可能とし、保険医の果たす役割は大きいと締めくくった。