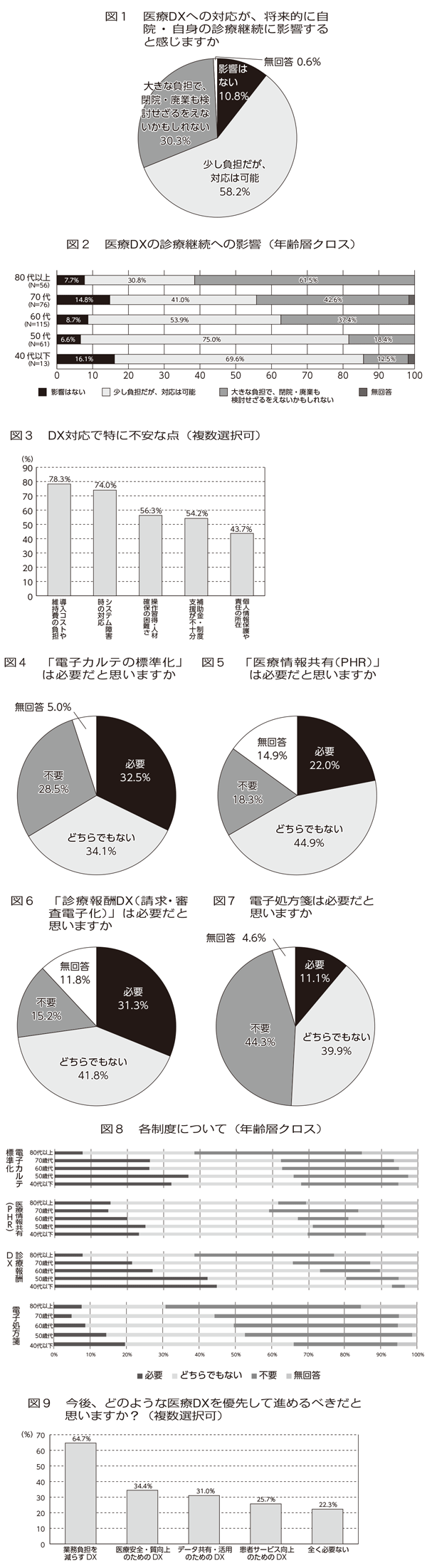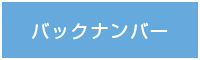2025年11月15日(2118号) ピックアップニュース
医療DXに関する意識調査結果
医療DX「負担に感じる」9割 コスト高や技術的対応に不安の声
政策部は、国の「医療DX」推進方針が医療現場に与える影響を把握するため、会員医療機関を対象に意識調査を実施した。調査は9月5日から9月30日にかけて行われ、323件(回収率5.3%)の回答を得た。
とりわけ60代以上の層で廃業を検討すると答えた割合が高く、年齢が上がるほど「DX対応の重荷」を感じる傾向が明確に表れた(図2)。
不安要因としては「導入コストや維持費」(78.3%)、「システム障害」(74.0%)、「操作習得・人材確保」(56.3%)が上位を占め、経営面と技術面の双方で大きな負担感が浮き彫りになった(図3)。
また、システム障害への懸念や、技術支援の不足も深刻である。「導入前に比較検討する知識がない」「相談できる専門人材がいない」との声が多く、現場は孤立したままDX対応を迫られている。
さらに高齢の開業医からは「あと数年で引退予定なのに投資を回収できない」「電子カルテ義務化の時点で閉院予定」といった現実的な悩みが寄せられた。紙カルテを使い続ける医療機関からは「対面診療では画面より患者を見たい」「紙で十分」といった診療哲学に関する意見も多く、単に「デジタル化の遅れ」とは片付けられない構造的課題が見える。
医療情報共有(PHR=パーソナル・ヘルス・レコード)については、認知70.6%と比較的高いが、「必要」としたのは22.0%にとどまり、「情報漏洩が心配」「運用負担が増える」との意見が多い(図5)。
診療報酬DX(請求・審査の電子化)については認知81.2%、必要31.3%、不要15.2%で、事務効率化への期待とともに、「審査の透明性が損なわれる」との懸念も見られた(図6)。
電子処方箋では認知率95.0%と最も高かったが、「必要」はわずか11.1%にすぎず、「不要」44.3%と否定的な回答が多数を占めた(図7)。高齢患者の対応や操作負担、導入コストが主な理由であり、最も抵抗感の強い分野となっている
全体として、若年層ほど「必要」と答える傾向が強く、年齢が上がるにつれて「不要」または「どちらでもない」との回答が増加している。
たとえば診療報酬DXでは、40代以下の必要との回答が約44.6%に上る一方、70代では21.3%、80代以上では7.7%にとどまった。医療情報共有(PHR)や電子カルテ標準化でも同様に、60代を境に「どちらでもない」「不要」が過半を占めるようになる。
一方で、電子処方箋については全年代を通じて否定的な傾向が際立っており、80代以上では「不要」が5割を超えている。
これは、高齢開業医ほど電子化による効率性よりも操作の煩雑さや患者対応への支障を懸念していることを示している。この結果は、DXに対する温度差が世代間で明確に存在し、現行の一律義務化方針が高齢層に過大な心理的・経営的負担を与えていることを裏づけるものといえる。
この結果は、現場が「実務改善型」のDXを求めていることを示している。すなわち、行政が想定する医療情報の共有のための処方薬情報やカルテの電子データ化とその収集ではなく、診療業務を円滑にし、医療の質を上げるための支援を望む声が多数である。
すなわち、DXは現場や患者にとって便利であれば自然に普及するものであり、国が強制する性質のものではない。導入を進めるのであれば、国の責任で十分な財政支援を行うべきである。
また、政策決定過程を透明化し、医療従事者や市民の意見を反映させる必要がある。マイナンバー制度との一体化は切り離し、アナログ対応を維持できる柔軟な制度設計を求める。さらに、個人情報の保護を徹底し、本人同意を原則とする仕組みを整えること、国が責任を持ってセキュリティ支援を行うことが重要である。
多くの医療機関が、制度の目的そのものよりも「導入コストと運用リスク」に目を向けざるを得ない状況にある。
国が果たすべき役割は、医療機関に一律の義務を課すことではなく、現場が安全に、そして確実に医療を提供できる環境を整えることである。
協会は今後も、医療現場の声をもとに「現場を支えるDX」の実現をめざしていく。
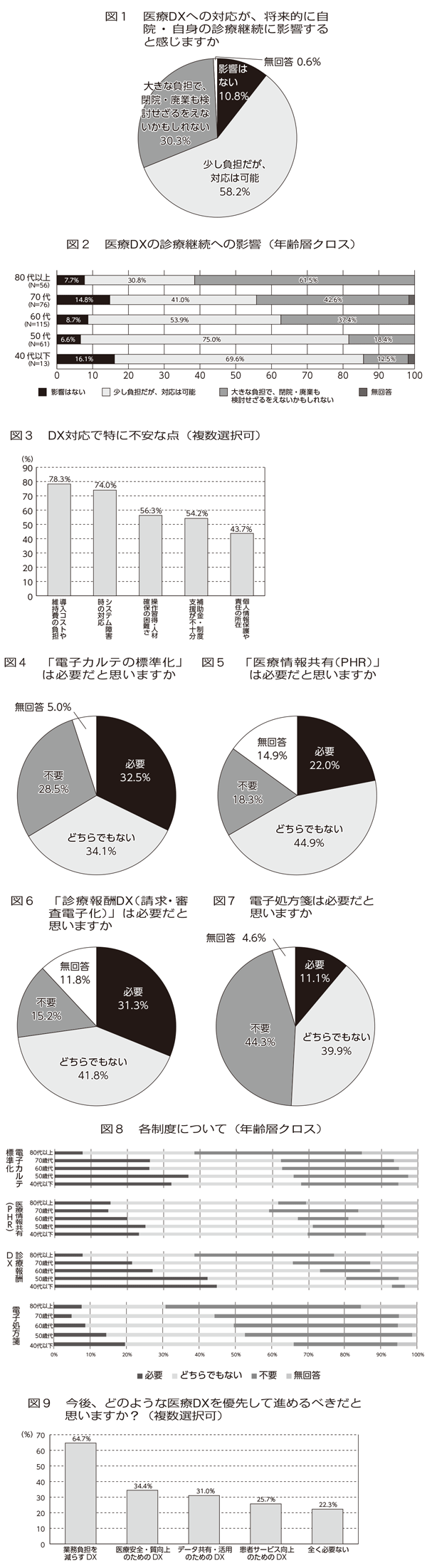
「廃業を検討」3割 経営への影響が深刻
調査の結果、「医療DXが診療継続に影響する」と答えた医療機関は全体の9割に達した。「少し負担だが対応可能」が58.2%、「大きな負担で、閉院・廃業も検討せざるを得ない」が30.3%、「影響はない」はわずか10.8%にとどまった(図1)。とりわけ60代以上の層で廃業を検討すると答えた割合が高く、年齢が上がるほど「DX対応の重荷」を感じる傾向が明確に表れた(図2)。
不安要因としては「導入コストや維持費」(78.3%)、「システム障害」(74.0%)、「操作習得・人材確保」(56.3%)が上位を占め、経営面と技術面の双方で大きな負担感が浮き彫りになった(図3)。
経営負担・制度不信・高齢化が壁に
自由記述では、医療機関が抱える困難がより具体的に示された。最も多かったのは経営負担に関する意見で、「補助金では到底足りない」「診療報酬が据え置きのままでは導入できない」との声が相次いだ。電子カルテや顔認証システムなど、国が推奨する設備の導入費用に対し、実際の補助額があまりに乏しいという指摘が多い。また、システム障害への懸念や、技術支援の不足も深刻である。「導入前に比較検討する知識がない」「相談できる専門人材がいない」との声が多く、現場は孤立したままDX対応を迫られている。
さらに高齢の開業医からは「あと数年で引退予定なのに投資を回収できない」「電子カルテ義務化の時点で閉院予定」といった現実的な悩みが寄せられた。紙カルテを使い続ける医療機関からは「対面診療では画面より患者を見たい」「紙で十分」といった診療哲学に関する意見も多く、単に「デジタル化の遅れ」とは片付けられない構造的課題が見える。
電子処方箋・PHRには慎重姿勢が多数
医療DXの各制度への認識・評価も尋ねたところ、電子カルテの標準化は89.8%が認知しており、「必要」とする意見が32.5%、「不要」28.5%、「どちらでもない」34.1%と賛否が分かれた(図4)。肯定的な意見は「情報共有や医療安全の向上につながる」とした一方、否定的な回答では「入力項目の制限で診療が硬直化する」「費用負担が大きい」との懸念が目立った。医療情報共有(PHR=パーソナル・ヘルス・レコード)については、認知70.6%と比較的高いが、「必要」としたのは22.0%にとどまり、「情報漏洩が心配」「運用負担が増える」との意見が多い(図5)。
診療報酬DX(請求・審査の電子化)については認知81.2%、必要31.3%、不要15.2%で、事務効率化への期待とともに、「審査の透明性が損なわれる」との懸念も見られた(図6)。
電子処方箋では認知率95.0%と最も高かったが、「必要」はわずか11.1%にすぎず、「不要」44.3%と否定的な回答が多数を占めた(図7)。高齢患者の対応や操作負担、導入コストが主な理由であり、最も抵抗感の強い分野となっている
年齢層で異なるDX制度への評価
各制度についての年齢層クロス集計では、それぞれに対する年齢層ごとの評価が比較されている(図8)。全体として、若年層ほど「必要」と答える傾向が強く、年齢が上がるにつれて「不要」または「どちらでもない」との回答が増加している。
たとえば診療報酬DXでは、40代以下の必要との回答が約44.6%に上る一方、70代では21.3%、80代以上では7.7%にとどまった。医療情報共有(PHR)や電子カルテ標準化でも同様に、60代を境に「どちらでもない」「不要」が過半を占めるようになる。
一方で、電子処方箋については全年代を通じて否定的な傾向が際立っており、80代以上では「不要」が5割を超えている。
これは、高齢開業医ほど電子化による効率性よりも操作の煩雑さや患者対応への支障を懸念していることを示している。この結果は、DXに対する温度差が世代間で明確に存在し、現行の一律義務化方針が高齢層に過大な心理的・経営的負担を与えていることを裏づけるものといえる。
「業務負担を減らすDX」を最優先に求める声
「今後どのような医療DXを優先して進めるべきか」という質問では、「業務負担を減らすDX」が64.7%と圧倒的に多く、「医療安全・質向上のためのDX」(34.4%)、「データ共有・活用のためのDX」(31.0%)が続いた(図9)。この結果は、現場が「実務改善型」のDXを求めていることを示している。すなわち、行政が想定する医療情報の共有のための処方薬情報やカルテの電子データ化とその収集ではなく、診療業務を円滑にし、医療の質を上げるための支援を望む声が多数である。
「任意・支援型のDX」を求める
保団連が2024年1月に決定した基本要求では、医療DXのあり方について明確な立場を示している。すなわち、DXは現場や患者にとって便利であれば自然に普及するものであり、国が強制する性質のものではない。導入を進めるのであれば、国の責任で十分な財政支援を行うべきである。
また、政策決定過程を透明化し、医療従事者や市民の意見を反映させる必要がある。マイナンバー制度との一体化は切り離し、アナログ対応を維持できる柔軟な制度設計を求める。さらに、個人情報の保護を徹底し、本人同意を原則とする仕組みを整えること、国が責任を持ってセキュリティ支援を行うことが重要である。
現場の声を政策に反映させるために
今回の調査は、医療DXが「便利な改革」である以前に、現場では深刻な経営・運用の負担として受け止められている現実を明らかにした。多くの医療機関が、制度の目的そのものよりも「導入コストと運用リスク」に目を向けざるを得ない状況にある。
国が果たすべき役割は、医療機関に一律の義務を課すことではなく、現場が安全に、そして確実に医療を提供できる環境を整えることである。
協会は今後も、医療現場の声をもとに「現場を支えるDX」の実現をめざしていく。