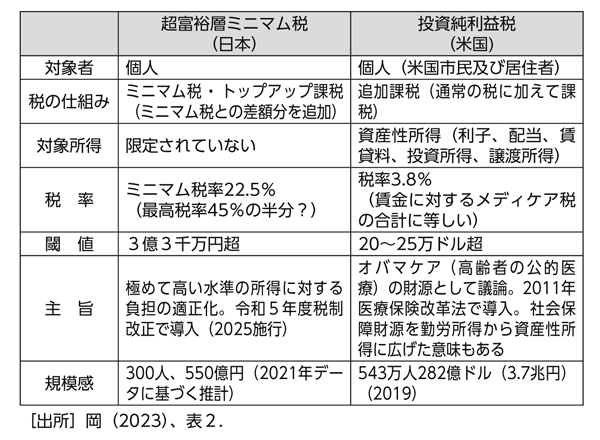2026年1月05日(2122号) ピックアップニュース
第106回評議員会特別講演 講演録
医療など「社会的投資」が格差と停滞を打ち破るカギ
京都大学公共政策大学院 諸富 徹教授

【もろとみ とおる】1968年生まれ。93年同志社大卒、京都大学大学院で経済博士号取得、横浜国立大助教授、京大准教授、京大大学院経済学科教授を経て2025年4月から現職。専門は環境経済学、財政学。著書に『環境税の理論と実際』『私たちはなぜ税金を納めるのか』。近著に『税と社会保障』『税の日本史』
はじめに
大学で財政学を専門にし、社会保障や税制を財政学の観点から研究している。社会保障の財源をどう確保するかはもちろん重要だが、同時に、集めた財源をどれだけ効果的に「人」に投資できるかということも、財政の大きなテーマになってきている。本日は、この「社会的投資」という考え方が重要になる背景を共有しながら、医療がどのように位置づけられるのかをお話ししたい。
なぜ「人」がこれほど重要になったのか
そもそも経済の中で、なぜ「人」への投資がこれほど重要になったのか。現代経済では、人的資本--知識や能力など「人」が持つ資源--の価値が飛躍的に高まっている。
20世紀の産業社会では、価値を生み出す「資本」といえば、工場の設備や機械だった。自動車の組み立てラインを思い浮かべると、工場の設備が中心であり、人はその設備のスピードに合わせて働く存在だったことが分かる。
しかし現在、工場設備よりも、新しい製品やサービスを生み出す「知識」、イノベーション、研究開発、ネットワーク構築といった「形のない資産(無形資産)」が、企業の競争力を決めるようになってきた。「資本の非物質化」という変化である。
現代の経済では、デジタル産業やAIなど、従来にはなかった広範な分野が急速に成長し、経済の中心が大きく変化している。
この変化をいち早く捉えたのが、マッハルプ、ダニエル・ベル、ドラッカーといった研究者たちだ。
ベルは『脱工業化社会』の中で、アメリカ経済の「サービス化」が加速することを統計的に示した。アメリカの製造業基盤が弱まり、いわゆるラストベルトの不況がトランプ政権の誕生につながったことは、その一つの象徴だと言える。
ドラッカーは『ポスト資本主義社会』の中で、最も重要な資源は「知識」であり、それを担うのが「知識労働者」だと述べ、これからのイノベーションは工業分野だけではなく、非工業分野から、より大きく生まれると予測した。アメリカの巨大テック企業はその典型例だ。
AppleのiPhoneは、Apple本社が直接製造しているわけではない。設計や開発といった「無形資産」こそが価値の源泉であり、実際の製造は外部企業が担っている。
スターバックスも良い例だ。店舗そのものは存在するが、スターバックスの本質的な価値は「空間」にある。落ち着いた内装、音楽、照明、仕事がしやすいWi-Fi環境--こうした要素自体がスターバックス特有の無形資産であり、人々はその「体験」に対価を払っている。空間そのものをデザインする知識や経験が価値を生んでいると言える。
このように現代の資本主義では、設備や機械といった「物質的な資本」から、ソフトウェア・プラットフォーム・ブランド・人材・研究開発などの「無形資本」へ資本の中心が移行している。無形資本への投資が有形資本への投資を上回る国も増えている。
無形資本の中でも、もっとも重要なのは「人間そのもの」だ。知識・経験・創造性・コミュニケーション・判断力--これらを持つ「人」こそが最大の価値の源泉であり、人への投資が社会全体の成長につながっていく。
人と人が出会う「知識の場」とインターネットの役割
価値創造は、一人ひとりの人的資本だけで生まれるわけではない。人間と人間の関係性の中で交わされるアイデアの交換やディスカッションから、新しいひらめきが生まれ、価値創造が起こる。したがって、人と人が出会い、新しい知識や考え方が生まれる「場」をどうつくるかも、現代の資本主義を考えるうえで非常に重要になってくる。この点を象徴しているのが、アメリカ経済で起きた変化だ。図1のように、アメリカでは1990年代以降、研究開発やソフトウェア、人材・組織への投資といった無形資産投資が、設備投資を上回る水準まで高まった。
象徴的なのが、90年代半ばのWindows95の登場だ。これによって、多くの人が初めてパソコンに触れ、扱えるようになった。それまでコンピュータは専門職の領域だったが、インターネットの普及と相まって「電子空間」が一気に広がった。誰でも情報にアクセスでき、学べるようになり、そこで人と人とがつながり、議論し、新しい価値をつくり出す--こうしたデジタルな「場」が生まれた。
その結果、プラットフォームやネットワーク、ブランドといった無形のものに投資することが、ビジネスの中核になっていく。
日本でもマンガ、アニメ、ゲーム、音楽、スポーツ、テーマパークなど、コンテンツ・エンタメ分野は、無形資本産業としてすでに大きな規模を持っている。これらはすべて、人間の創造性と経験に依拠した無形資本の集積として捉えることができる。
技術進歩と格差拡 大スキルを持つ人と持たない人
一方で、このような無形資本を中心とした経済への転換は、格差の拡大とも結びついている。フランスの経済学者トマ・ピケティらの研究が示すように、80年代以降、多くの先進国で上位1%の所得シェアが上昇してきた。背景にあるのは、MITの労働経済学者オーターらが「スキル偏向的技術進歩」と呼ぶ現象である。コンピュータを使いこなし、新しいビジネスを生み出せる高スキル層と、逆にパソコンやデジタル化によって仕事が置き換えられてしまう中間層や単純労働層との間で、賃金や雇用機会に大きな差が生まれてきた。
70~80年代、事務作業や定型的なオフィスワークの多くがコンピュータに代替された。かつては地図に事件現場を手書きで記入していたような仕事が、今やGISや検索システムで瞬時に処理される。こうした変化の中で、「中位のスキルの仕事」が削られ、高スキル職と低スキル職だけが残る「雇用の二極化」が進んだと指摘されている。
その結果、賃金の分布は「真ん中がへこむ」形になり、高スキルの専門職(賃金上昇)と、AI・機械化が難しい対人サービス職(賃金は低いが需要は残る)の両端だけが残る構造が生まれた。さらに、この「真ん中」の仕事を失った人たちが低スキル労働市場に流れ込み、競争が激化して賃金がさらに下落するという悪循環も生じた。
直近では、AIが同じ問題をさらに先鋭化させる可能性がある。AIを使いこなして仕事の生産性を高められる人と、AIに仕事を代替されてしまう人とのあいだで、賃金・雇用の差が広がるリスクがあるからだ。
ここで重要なのは、格差の原因を「個人の努力不足」に還元してしまわないことだ。問題はむしろ、社会全体として必要なスキルを身につける機会を、どれだけ公平に提供できているかにある。
だからこそ、教育、職業訓練、生涯学習、そして健康・医療への投資といった「人的資本への社会的投資」が重要になってくる。これらは、技術変化に適応できる人を増やし、格差拡大を抑えつつ、経済全体の生産性を高めるための基盤になる。
賃金が上がらない 投資が進まない日本
では、日本はどうか。賃金が90年代からほとんど伸びず、欧米諸国が右肩上がりのなか、日本だけが横ばいになっている。さらに問題なのは、設備投資が伸びていないことだ。バブル崩壊後は更新投資が中心となり、未来志向の投資が十分に行われてこなかった。
90年のバブル崩壊のあと、日本は約15年もの間、後処理に追われ続けた。日本企業はひたすら過去の借金返済や財務再建に追われ、未来への投資に回す余力がなかった。
その間に世界は大きく転換した。産業の中心は「有形の資本」から「無形の資本」へ移り、知識・IT・データを基盤とする経済へと進んでいった。
Windows95をきっかけに一般家庭にパソコンが普及し、世界は急速にデジタル化したが、日本はその変化に大きく遅れを取ってしまった。日本はパソコンを「新しい家電製品の一つ」と捉え、テレビや家電の延長線で扱ってしまったのである。
株主重視への転換と「人への投資」の減退
日本の停滞を説明するうえで、もう一つ重要な要因がある。2000年代以降、日本企業は急速に「株主重視」へ転換した(図2)。コーポレートガバナンス改革が進み、配当を増やし、社外取締役を置き、株主が評価しない経営者は退陣させるという仕組みが広がった。かつて日本企業は「メインバンク型」の資本構造で、銀行が長期的視点で企業を支える環境があった。そのため、人的資本投資や研究開発に比較的積極的だった。
しかし2000年代以降、短期的な株価・配当が重視されるようになった結果、配当は急増し、内部留保も積み上がったが、人的資本投資(教育訓練費)は大幅に減少し、研究開発も横ばいという状況が続いている。日本企業は「人ではなく株主へお金を回す会社」になってしまった。
これは企業の短期的な株価にはプラスでも、生産性の頭打ち、革新の停滞、若者の賃金が上がらないこと、国内の成長力の低下といった深刻な弊害を生み出す。人的資本を軽視し、株主への分配を優先すると、日本企業の強みであった「長期の育成」「現場力」「組織の熟成」を弱めてしまうからだ。
以上をまとめると、日本はバブル後処理で投資のタイミングを逃し、無形資産の世界的な拡大に乗り遅れ、株主偏重により人的資本投資が削られ、賃金も成長も停滞したという構図になる。この流れを踏まえると、次に紹介する「スウェーデンの社会的投資国家モデル」が、なぜ日本にとって重要なヒントになるのかが見えてくる。
スウェーデンの成長戦略と人的資本投資
図3を見ると、90年以降、スウェーデンの経済成長率は日本を大きく上回り、実に30年以上にわたり、日本より高い成長を続けている。
スウェーデンでは賃金も継続的に上昇している。賃金上昇は企業にとってコスト増だから、成長の足を引っ張るように見える。しかし実際には、賃金上昇、高い生産性、持続的な経済成長が同時に起きている。賃金が高くても成長できる構造を作り上げてきたということだ。その核心にあるのが、人的資本への継続的な投資である。
人的資本投資とは、新しい知識を身につけること、技術をアップデートすること、医療・福祉・教育など職場ごとのスキルを磨き続けることを「個人任せ」ではなく社会全体で保障するという考え方だ。医療現場を例に取れば、医療機器は常に更新され、治療法も日々変わる。それに合わせて医師・看護師・技師・事務などさまざまな職種のスキルを、絶えずアップデートしなければならない。
これは企業や病院が自前でやるには限界がある。そこで政府が責任を持ち、教育・研修の機会を保障し、公的資金でスキル更新を支援する。これが社会的投資の基本思想だ。人的資本を「コスト」ではなく「投資」として扱う発想が徹底していると言える。
ケインズ理論と「人を守る」社会保障
スウェーデンがなぜ「人への投資」をこれほど重視するのか。その背景には、歴史的な転換点がある。その一つがケインズ理論の登場である。「いくら努力しても抗えない巨大な経済の波」の存在を示した大恐慌を経て、ケインズは、人々が食べて生きていくための所得を確保するのは国家の責任であり、市場任せでは失業は解決できないと主張した。国家が雇用政策を行い、景気の防波堤にならなければならない--ここから現代の社会保障政策の基礎が形づくられていった。
スウェーデンの社会保障の中核は、「家を失わせないこと」にある。失業しても住居を失わない、家族が生活を維持できる、その間に公的な職業訓練を受けられる。個人に蓄えがなくても、不可抗力に対して社会が支えるという考え方だ。
企業が倒産したときの扱いにも日本との違いが表れる。日本では、日産とルノーの関係のように「会社を守る」ことが優先される。一方スウェーデンは、「会社は守らない。人を守る」という明確な哲学を持っている。ボルボが外資に買収され、中国資本のもとで再生したケースは象徴的だ。企業は変わってもよい。その代わり、雇用された人は国家が守るというスタンスである。
企業が倒産すれば、いったん労働者は失業する。しかしスウェーデン政府はまず生活保障を行い、次に職業訓練を提供し、新しいスキル獲得を徹底的に支援したうえで、成長産業へ再就職につなげる。この仕組みによって産業の新陳代謝が早く進み、IKEA、H&M、Spotify、Skypeといった新しい企業が次々に生まれている。
社会的投資国家とは何か--人への投資を公的に支える
こうした経済構造の変化と歴史的経験を踏まえると、政府がどこに投資すべきかが明らかになる。「人」を育てることが未来の成長につながるという考え方が「社会的投資国家」である。社会的投資とは、教育、職業訓練、医療・予防、幼児教育・保育、健康格差対策など、人的資本を高める分野を国家が長期的に支えることを指す。医療はその中心に位置づけられる。健康でなければ知識を獲得することも働くこともできず、人的資本の基盤そのものが損なわれてしまうからだ。
重要なのは、人的資本投資の成果が個人だけにとどまらないという点である。良い人材が育つと、周囲の人のスキルも高まり、職場全体の生産性が上がり、新しい知識が連鎖して広がる。サッカーのチームと同じで、一人だけ上手くなっても意味はない。仲間も一緒にスキルを上げて、連動性が高まってこそ結果が出る。だからこそ、公的に支援する意味があるのだ。
日本の社会保障財政と社会保険料の上昇
ここからは、日本の社会保障財政をどのように再構築していくべきかという問題に移る。社会的投資拡大には、当然ながら財源が必要になる。日本の社会保障支出は、医療(高齢医療を含む)と年金+介護に約8割が集中している。一方で、子育て支援、労働市場政策(再就職支援・職業訓練)、若年・現役世代への教育投資などへの配分は相対的に薄く、日本は「現役世代の社会保障が薄い国」になっている。
日本の社会保障は、「税」と「社会保険料」の二本柱で支えられている。近年、基礎年金の国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げ、就学前教育の無償化を進めるなど、税の比率は高まったが、それ以上に社会保険料収入が増え、いまや税収より社会保険料収入のほうが大きくなっている。
社会保険料率は90年代から一貫して上昇し、現在では労使折半で約30%、労働者は約15%が給与から差し引かれている。「手取りが減った」という国民感覚の背景には、この社会保険料負担の増大がある。そのため政府は、社会保険料のこれ以上の引き上げは困難であり、むしろ一部を引き下げるべきだという議論も示している。
社会的投資の財源をどう確保するか
社会保険料に限界が見えるなか、財源確保の議論は大きく三つの方向に進んでいる。
一つは消費税の引き上げである。財務省は一貫してこの方向を主張しているが、政治的反発が強く、現実には難しい局面がある。
二つ目は、窓口負担の見直しだ。患者の金融資産(預貯金など)を把握し、資産の多い人の負担割合を引き上げる案だが、実務的には金融資産の把握が極めて困難であり、厚労省も慎重な姿勢をとっている。
三つ目が、欧米型の金融所得課税の強化である。フランスのCSG(社会保障税)や、アメリカのオバマケア財源としての投資収益課税など、配当や株式譲渡益などの金融所得に依拠する方式が国際的には広がっている。
アメリカでは、社会保障財源の一部を「投資純利益税(Net Investment Income Tax)」が担っており、賃金税やメディケア税とは別に、資産性所得に対して負担を求める仕組みが整備されている。課税対象は、①その人が得た投資純利益そのもの、または②修正後調整総所得(MAGI)が一定額を超える部分の金額--この二つのうち、より小さい方で決まり、年間所得が高いほど負担が生じやすい構造になっている。投資純利益には、利子・配当・賃貸などの資産所得、消極的活動や金融商品取引による所得、さらには事業用資産を除く財産の売却益が含まれ、そこから所定の控除を差し引いた額が課税ベースとなる。
こうした仕組みの特徴は、労働所得ではなく、資産性所得に広く薄く負担を求める点にある。人的資本への社会的投資を拡大しようとする場合、勤労世代の負担に偏らず、金融所得を有する高所得層に応分の負担を求めることが合理的であり、アメリカではすでにこの枠組みが機能している。
一方、日本では金融所得への課税が限定的であり、現行制度のなかで最も欧米型に近いのは、いわゆる「ミニマム税」と呼ばれる仕組みである。これは、一定以上の高額所得者について、まず通常の計算による所得税額を求め、そのうえで「最低限この額以上の税負担は必要だ」とする基準税額(ミニマム税額)も別途計算し、通常の税額がミニマム税額を下回った場合には、その差額を追加で納税させる制度である(表)。
ただし日本のミニマム税は、年間所得が3億円を超えるようなごく一部の超富裕層にしか適用されておらず、財源確保という観点ではほとんど機能していないのが実情である。これを欧米並みに拡張し、対象となる所得層を広げ、かつ金融所得も包括的に捕捉できる仕組みに改めれば、社会的投資国家へ転換するうえで極めて有力な財源となり得る。
労働所得への負担が限界に達し、社会保険料の引き上げも困難になりつつある現在、日本が社会的投資を拡大するためには、資産性所得に対して適正な負担を求める新たな税体系を整備する必要がある。ミニマム税の拡張は、その第一歩として位置づけられるべきだと考えている。
社会的投資国家へ
ここまでお話ししてきたことをまとめると、現代の資本主義は無形資本を中心とする経済へと移行し、人的資本への投資こそが成長のカギになっている一方で、技術進歩はスキルの差を拡大させ、格差を広げる力も持っている。日本は、バブル後処理と株主偏重の中で人的資本投資を削り、賃金も成長も停滞してきた。社会保障支出は高齢部門に偏り、現役世代・子ども世代への投資が薄い構造になっている。
だからこそ、教育、医療、キャリア支援、保育、地域共生などへの「社会的投資」こそが、格差と停滞を打ち破るカギになる。スウェーデンの経験は、「企業ではなく人を守る」「人的資本をコストではなく投資として扱う」ことで、高い賃金と成長を両立できることを示している。
医療を「費用」ではなく「社会的投資」として位置づけ、経済・財政・社会保障全体の流れの中で考えてもらえればと思う。健康でなければ知識を獲得することも働くこともできない。医療は、人的資本の基盤そのものを支える、もっとも根幹的な社会的投資である。
図1 マクロ経済における資本主義の「非物質化」
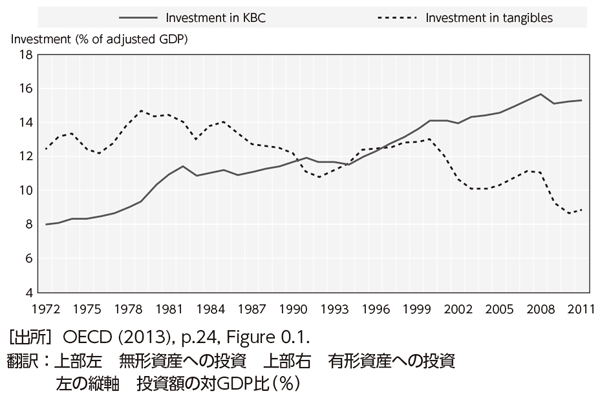
図2 増加する「配当」と「内部留保」
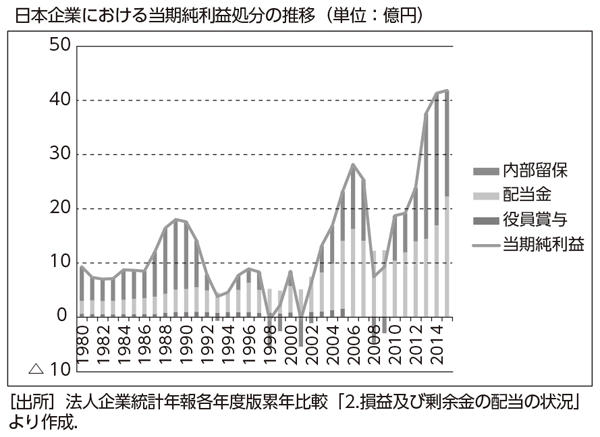
図3 日本、アメリカ、スウェーデンの実質経済成長率の推移
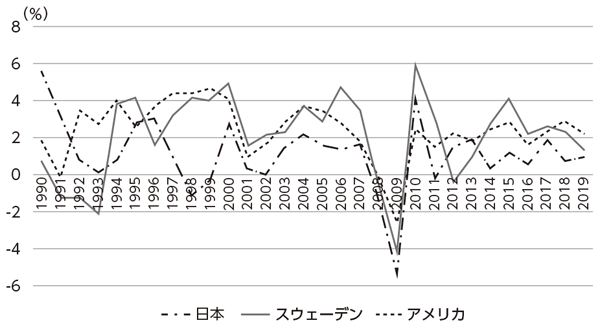
表 日本のミニマム税とアメリカの投資純利益税