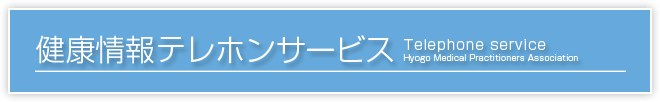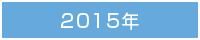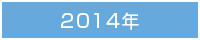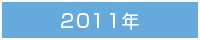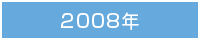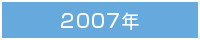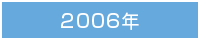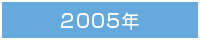2025年7月
【金土日】神経症と精神疾患
神経症という言葉から、皆さんはどんなイメージを思い浮かべられるでしょうか?情緒が不安定で、落ち着きない素振りで、ちょっとした出来事を気にする人を思い浮かべるでしょうか?
神経症は、もともとノイローゼとも呼ばれていましたが、今はあまり使われていません。
神経症には、「不安神経症」「強迫神経症」「抑うつ神経症」等、様々な種類があります。
精神科の辞典によれば、精神障害の中で、身体的には元気だが心理的、環境的な原因により起こる疾患となっています。つまり、その人の人格が保たれており、意志の疎通ができ、病識つまり自分が病気であることの自覚があり、不安・強迫・恐怖など、気分が不安定な状態が主なものであり、周りの人も理解できる症状と定義しています。
その疾患の症状が、周りの人にとって理解可能であれば神経症、理解が不可能であれば精神疾患というのも、やや乱暴な区別ですが、概ね間違いではないでしょう。
もう少し精神疾患と神経症の違いを述べましょう。
精神疾患は、主に統合失調症と、感情障害(いわゆる双極性障害)を表します。その例を説明すると、統合失調症の場合、周囲の人が聴こえていない声が聴こえる「幻聴」があります。これは周りの人にはには理解しがたいことです。
それに対して神経症の症状は、周囲に理解されやすいと言えます。例えば閉所恐怖という症状の一つに、電車に乗ってトイレに行けないのではないかとの恐怖があります。トイレのない普通電車には乗れません。でもトイレ付きの新幹線などには乗れます。このような理由で原因の分かる症状であれば、周りの人も分かります
大切なのは、神経症が精神疾患に比べて軽い病気と思わないことです。何十年も神経症の拘りに苦しむ人がいます。逆に精神疾患を患っていても、適切に通院加療を行っていれば社会生活においてなんら支障のない人もたくさんいます。
神経症の症状は個人個人によって様々です。その人特有の症状を理解して、適切な治療を受けることが大切です。