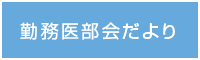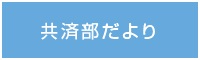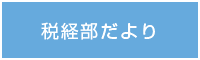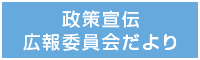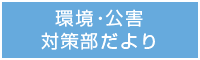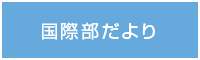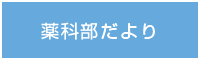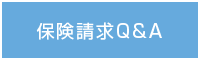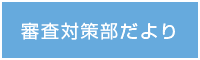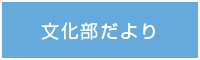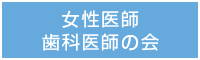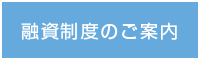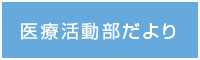政策宣伝広報委員会だより
地域の実情に即した地域医療構想と診療報酬改定を 但馬医療の実態ふまえ県に要望
2025.07.25

県(右側)に要請する綿谷地域医療部長(左2人目)・大澤理事(左端)
協会からは綿谷茂樹地域医療部長(理事)、大澤芳清理事が参加。県からは、保健医療部医務課の高見和典副課長、同課企画調整班の築本健史班長、同部総務課の村田拓也企画班長が対応した。
今回の要請は、3月23日に協会が豊岡市内で行った「地域医療を考える懇談会」を受けたもの。同懇談会では、公立豊岡病院から、地域の高度救急を一手に担う一方で、高齢の患者を長く入院させざるを得ず、「平均在院日数」が長くなる問題、診療所から、慢性期や回復期の病床が不足し、急性期後の患者を、在宅で直接受け入れざるを得ないケースが相次いでいることが報告された。結果、豊岡市の在宅看取り率は25.6%と全国の中規模都市で最も高い。また、政府の長年にわたる低医療費政策と急激な物価上昇で、医療機関の存続そのものが危ぶまれるという意見も出された。
要請では、綿谷部長が、こうした議論を紹介し、「地域医療構想」を現場の実情に即して改めることを求めた。
これに対し、県側は、「国から地域医療構想の新たなガイドラインが今年度中に示される見込み。在宅医療に合わせたより小規模な圏域での構想や、医療従事者の確保等のためのより広域的な区域設定の必要性も指摘されており、これらを踏まえて、県として柔軟な新しい地域医療構想を策定していきたい」とした。また、「近畿厚生局の仲介で、京都府とは、情報共有、情報交換を行っている」と現状の取り組みを紹介した。
病院の深刻な経営危機を訴えた大澤理事に対しては、「医療機関の経営がより厳しくなっている状況は強く認識している。診療報酬で本来補うべき費用が補いきれていないので、診療報酬を物価に応じて適切にスライドさせる仕組みや、臨時の改定などの柔軟な対応が必要と思っている。機動的な補助制度の導入も求められる。そのため、全国知事会などを通じて国に対し、昨年度から特に今年度にかけて要望活動を繰り返している」と回答した。
最後に綿谷部長が「地域の住民を守りたいという思いは同じと思う。県民のために一緒に頑張っていただけたらと思う」と締めくくった。
協会では、引き続き医療機関の窮状と地域の声を、県などに伝えていく。