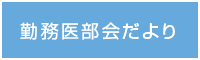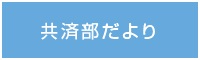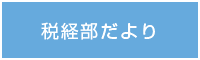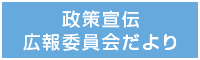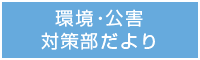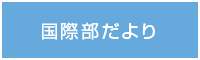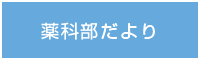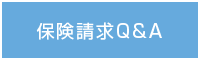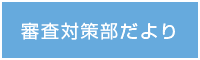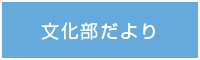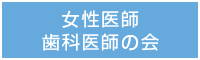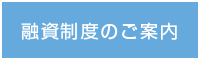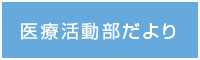政策宣伝広報委員会だより
特別インタビュー 県立はりま姫路総合医療センター院長 木下 芳一先生に聞く 地域医療の最前線から--- 厳しい経営環境、診療報酬引き上げを
2025.09.25

【きのした よしかず】1980年神戸大学卒業、87年ミネソタ州メイヨークリニックへ留学(リサーチフェロー)、97年島根医科大学第2内科教授、2002年同大学附属病院光学医療診療部部長、03年島根大学医学部第二内科学教授、2004年島根大学医学部副学部長、07年同大学医学部学部長、12年同大学医学部附属病院副院長、19年製鉄記念広畑病院病院長、20年県立姫路循環器病センター院長、22年から現職
西山 今日はお忙しい中ありがとうございます。早速ですが、日本中で公私を問わず病院の赤字が問題になっています。貴院の状況を教えてください。
木下 開院以来、年間赤字額は年々小さくなっていますが、いまだ赤字経営が続いています。赤字の原因は、この20年間ほど診療報酬がほとんど上がっていない一方で、2020年代に入ってから人件費と物価が急速に上昇したことです。2020年当時と比べると、どちらも約10%上がっています。
例えば、当院の年間収入規模はおよそ300億円です。開院前には、費用300億円に対して収益も300億円とし、収支均衡を見込んでいました。しかし開院後には費用が10%増え330億円となり、収入は300億円のままなので、毎年30億円の赤字を抱える構造になっています。
さまざまな工夫で圧縮していますが、現状でも約19億円の赤字が残っています。
患者への配慮、医療安全と収益性のジレンマ
木下 当院ではすでに診療科ごと、疾患ごとの収益性分析を終えており、どこを削れば収益が改善するのかは分かっています。しかし、それを実行するかどうかは問題です。収益性を優先して支出が大きな部分をむやみに削減すれば、患者さんに優しく、安全な病院ではなくなるのではないかと考えています。
例えば当院は大学病院に準じた診療密度を持つDPC特定病院群に属しています。同群の約180病院で鼠径ヘルニア手術の収益性を比較すると、当院はかなり下位にあります。
詳しく分析してみると、収益性の高い病院は血液検査やX線撮影を入院ではほとんど行っていません。麻酔後の肝機能等の確認のために血液検査は必要と考え、当院では入院中に実施をしています。収益性の高い病院では手術後すぐに退院させ、外来で検査を行い、異常があれば再入院させる方式です。入院中の検査は包括評価ですが、外来では出来高払いです。
また当院では、ガーゼカウントに加え、X線で確認できるガーゼを使用し、X線撮影で術後のガーゼ遺残がないかを確かめています。ガーゼ残存は決してゼロではありませんので、安全を最大限保障するにはこの方が良いと考えています。また、鼠径ヘルニア手術は若手医師が担当することが多く、経験不足によるトラブルの可能性もゼロではありません。だからこそ安全性を徹底する必要があります。
患者さんを早期退院させ、万一腹痛が出れば翌朝外来で採血してしばらく待たせる--患者さんの利便性や安全性、快適性を犠牲にして収益性を高めるとなれば、財政当局も医療の消費者である患者さんも含めて、その必要性を議論したいところです。

聞き手
西山 裕康理事長

綱島 武彦評議員

石橋 寛之理事
基幹病院特有の〝持ち出し〟
木下 たとえば総胆管結石の内視鏡手術は、当院は県立尼崎総合医療センターや神戸市立医療センター中央市民病院と同程度の件数を行っており、収益性は3病院の中では良い方です。しかし、それでも実際の利益率はマイナスになります。理由の一つは、当院の前身である県立姫路循環器病センターのころから持続する患者さんの特徴にあります。従来から心疾患患者を多く診てきたため、心不全を合併した患者さんや、抗血栓療法薬を服用していて出血リスクの高い患者さんが地域から集中するのです。その結果、在院日数や検査、投薬が増えますが、副傷病名にこれらの対応が含まれなければ包括評価に吸収され、利益が出にくくなります。
西山 医師養成や臨床研究の分野はいかがでしょうか。
木下 研修医の人件費は年間2億円ほどかかりますが、彼らは直接には収益を生みません。完全な持ち出しですが、地域の医師を育てるためには不可欠です。
さらに臨床研究も重要な使命です。臨床研究に係る収入は年間1億円程度ですが支出も多く、現状では収益を生む部門というわけではありません。それでも研究・開発に関する環境を整えることで、研究意欲のある優秀なベテラン医師が集まり、病院全体の質が高まります。研修医の教育レベルも向上しますし、患者さんにとっても新しい治療選択肢が増えます。
たとえば、一般的な治療をすべて試しても効果がないがん患者さんに対して、米国では行われているが日本では未承認の治療を、治験という形で提供できる場合があります。このような研究的な治療に参加を選ぶ患者さんもおり、満足度の向上につながっていると感じます。
ベースアップ評価料のミスマッチ
木下 厚労省はベースアップ評価料で2024年度に前年度比2.5%、2025年度に2.0%のベースアップをめざしています。しかし当院は県直営病院のため、県人事委員会勧告に従いますので2024年度は2.78%の引き上げでした。さらに今年度は3.62%程度の引き上げとなりそうです。加えて当院は若い職員が多く、勧告が若年層に重点を置くため、負担はさらに大きくなっています。
昨年だけで人件費は約7億円増加しましたが、評価料収入は2億円程度で、差し引き5億円のマイナスです。公立病院にとって評価料では対応しきれないことは明らかです。
石橋 職種を限定したのも問題で、私どもの病院でも明らかに不足です。
ダウンサイジングは必要か-高稼働の700床体制
木下 当院は、2015年頃に策定された基本計画に基づいて誕生しました。製鉄記念広畑病院と県立姫路循環器病センターを統合し、大型病院をつくるべきだとされた背景には、西播磨・中播磨地域の深刻な医師不足がありました。人口当たりの医師数は島根県の隠岐の島と同程度に少なく、救急搬送の「搬送困難例」も県内で最多でした。
その原因を探ると、当地域の進学校から年間100人以上の学生が医学部に進学しているにもかかわらず、その多くが地元に戻っていませんでした。理由を聞き取ると、「専門医を育てる医療機関が地域にない」ということがわかりました。
そこで、大学病院のように医師を育成できる規模と人材を有する病院を整備する必要があると判断されたのです。大学病院は通常600床以上の病床を有しています。さらに「救命救急を重視し、あらゆる救急患者にも対応できる体制」を整えるには全診療科が設置されていることが不可欠です。形成外科のように整備が難しい診療科も、断指や神経損傷の再接着術に不可欠です。結果として700床以上の大規模病院が必要と判断され、現在の規模となりました。当初の目的を忘れ、事後的に経営面だけを見て縮小を議論するのは乱暴です。
仮に今、私どもの病院の稼働率が低ければ縮小を検討する余地もありますが、はりま姫路総合医療センターの7月の病床稼働率は93%。平日は満床に近く、16室の手術室や5室のカテーテル室もほぼフル稼働です。
病院機能の大部分がフル稼働しており、現状に照らせばダウンサイジングの余地はありません。
綱島 今後の改善策について教えてください。
木下 私は、土曜・日曜の医療提供をさらに充実させたいと考えています。地域住民のライフスタイルは多様化しており、土日に仕事をする人や夜間勤務の人も増えています。神戸大学医学部附属病院でも土曜や祝日に予定手術を実施しています。
当院ではすでに休日にリハビリを行い、あるいは家族と一緒に栄養士の食事指導を受け、自宅でも入院時と同じ食事を再現できるようにしています。薬剤師による服薬指導も休日に家族同伴で行う取り組みを始めました。さらに10月からは、外来患者さん向けに土曜のMRI検査も実施します。こうした工夫で、休日の稼働率低下を抑え、地域住民にとってより使いやすい体制を整えつつあります。
ただし、これらは短期的に見ると必ずしも収支改善に直結するわけではありません。私はむしろ「経営改善を目的に病院を運営する」という発想自体が誤り、主客転倒だと考えています。
病院の使命は地域住民により良い医療を提供し、利用しやすい存在になることです。その結果として黒字が出れば、病院をよく利用いただき「とても良かった」、病院の利用が少なく赤字なら「残念だった」「改善が必要だ」程度にとどめ、経営は目的ではなく良い医療提供の後からついてくるものであるべきだと思います。
もちろん、土日に外来診療を実施すれば診療報酬上時間外は加算できず、休日手当の支出も増えるため短期的な収支は悪化するかもしれません。今後は人口減少のため、外来患者さんや入院患者さんはどんどん減少していくと予測されています。しかし、医療レベルの高さに加えて、利便性を高め、患者さんに優しい病院であり続ければ、結果として地域から選ばれ、長期的に収支もプラスになると考えています。
西山 政府は医療機関の経営効率化のため、医療DXを進めています。経営改善につながるでしょうか。
木下 当院でもAI問診や胸部X線・内視鏡のAI読影を導入し、電子カルテに生成AI文書作成システムを組み込むことも検討しています。しかし、それでも時間外労働は減っていません。DXは魔法の杖ではありません。特定研修を受けた看護師の活用などのタスクシフトも行っていますが、限界があります。
診療報酬改定に向けて医療を守る国民的議論を

兵庫県立はりま姫路総合医療センター(愛称:はり姫)
2022年5月、県立姫路循環器病センター(330床)と製鉄記念広畑病院(392床)が統合してできた736床の姫路・西播磨地域で最大規模の病院。33の診療科、16室の手術室、最新の医療設備を持ち、高度専門医療、救命救急医療を担うとともに、医療人材の育成に力を入れている
木下 ただし、国には財源問題があります。国民は「世界最高水準の医療を、公的保険制度で無制限に享受できる」と信じています。しかし現状の分配方法では現在のレベルは維持できません。そのことを地域住民や国民に理解してもらい、医療費や防衛費、教育費など国の予算については国民的な議論が不可欠です。
西山 確かにその通りです。診療報酬改定に向けて望むことはありますか。
木下 2026年度の診療報酬改定で最も期待するのは、DPC特定病院群の評価改善です。現在、DPCで最も評価が高いのは大学病院、次が特定病院群です。当院もその一つで、手術数や医療投下量は大学医学部附属病院と同水準です。E難度の手術や10万点以上の高額手術も同程度に実施しています。機能は大学病院並みであるため、評価も同等にしていただきたいと思っています。われわれ病院当事者以外からの要望も有効だと思います。
西山 私たちの要望に取り入れて、実現を目指したいと思います。
私たちは診療報酬改定に向け、「地域医療を守るため、緊急財政措置と診療報酬の大幅引き上げを求める署名」を集める予定です。県内医師の半数を目標にしていますので、ぜひご協力をお願いします。
木下 ご意見には賛同します。
西山 本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。