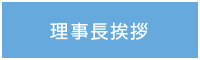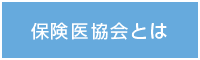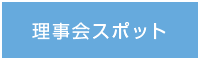理事長挨拶
新年挨拶 2025年1月
「乙巳」の年
柔軟に発展していく一年に

理事長 西山 裕康
会員の皆様、明けましておめでとうございます。昨年中は、協会の諸活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
昨年は元日に能登半島地震が発生しましたが、1年たった今でもその復旧の遅れには憤りを感じずにはいられません。また阪神・淡路大震災後30年の節目の年でもあり、南海トラフ地震を念頭に、記憶を風化させずに、対策を怠ってはなりません。
昨年4月の診療報酬改定では、私たちの要求に反し、5回連続の本体マイナス改定となりました。「病院の経営危機」の原因が「診療所の良好な経営」にあるかのような、医療現場の実態を省みない根拠の薄い印象操作が行われ、医療界に分断を持ち込みました。長く続く低医療費政策に加え、物価高騰や人件費の上昇、従業員不足により、多くの医療機関の経営は悪化傾向が続いています。
また「医師不足」は「偏在」にすり替えられ、開業への規制的手法も行われます。そもそも少子化、地方衰退、地域間格差に対して有効な手を打てず、そのしわ寄せを勤務医の勤務先選択や保険医資格に押し付けるのは大いに疑問です。
医療費抑制政策が是とされ、財政赤字の主因を社会保障費とし、安直な政治決着が可能な診療報酬を抑制する一方で、「防衛」「DX」という言葉さえあれば、財源が後付け可能な手法が容認されています。まずは国民の生活を豊かにする政策を優先しなくてはなりません。昨年末の総選挙では、与党が過半数割れとなりましたが、医療費抑制政策の転換のためには、政権交代以外にどのような方法が期待できるのでしょうか。
昨年12月には保険証の新規発行が停止されました。決定過程も不透明なうえに、「アメとムチ」で政策を強引に推し進めるのは、政財官の強固な結びつきと利権確保といった本音が透けて見えます。どのような政権であっても、国民の大半が反対する政策を「悪しき前例」として継続させてはなりません。
今でもマイナカードを持っていない人は約3000万人、保険証として利用していない人は1億人近く存在します。今後利用率が上がり、あるいは保険証の期限切れに伴い、窓口でのトラブル増加が懸念されます。協会は「マイナ保険証反対」活動を続けますが、同時に会員や患者さんの利便性を第一に考え、トラブル防止やその解決にも対応したいと思います。
最後に、昨秋の県知事選挙に、当会の大澤芳清理事が立候補した際には、たくさんの方々から温かく力強いご支援を頂戴し、重ねて感謝いたします。残念な結果になりましたが、今後につなげる糧としたいと思います。
本年は、十干の「乙(きのと)」と十二支の「巳(み)」が組み合わさった「乙巳(きのと・み)」です。乙は「木」の要素を持ち、草木がしなやかに伸びる様子や横へと広がっていく意味があり、巳は神様の使いとされ、脱皮を繰り返すことから長寿や健康、不老不死のシンボルともされているとのことです。暗い話ばかりのご挨拶となりましたが、本年は、「再生や変化を繰り返しながら、柔軟に発展していく」年にしたいと思います。
皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます。
第105回評議員会挨拶 2025年5月

兵庫県保険医協会
理事長 西山 裕康
本日はお忙しい中、評議員会にご出席いただき、誠にありがとうございます。また、日々の診療や業務にご多忙の中、協会の活動にご理解とご協力をいただいております評議員の皆様に、改めて心より感謝申し上げます。
私たちを取り巻く医療環境は、これまでに経験したことのない大きな危機に直面しています。低医療費政策に加え、物価高騰、人件費上昇、医療人材確保の困難さが重なり、制度のあらゆるひずみが現場に集中しています。
このため、診療所・病院を問わず多くの医療機関が深刻な経営難に直面し、医療従事者の疲弊も深刻化しています。
私自身の医師としての過去を振り返っても、これほどまでに厳しい状況は経験がありません。
こうした事態の背景には、長年にわたって続いてきた「医療費亡国論」に基づく「医療費抑制政策」が存在します。40年以上前に登場したこの理論が、誤った前提に立ちながらもなお、制度設計の根幹に据えられ続けていることは、看過できるものではありません。
診療報酬制度のあり方もまた、現場の実態から大きく乖離しており、機能不全に陥っていることは明白です。
いま、6割を超える病院が赤字、全国の大学病院も多くが厳しい経営状況にあり、兵庫県直営の10病院はすべてが2年連続赤字で、民間病院に置き換えれば倒産が目前です。内部留保は枯渇し、医療への再投資は進まず、ある日突然、地域の基幹病院が消える──そんな未来すら現実になりかねません。
さらに、医師不足を「偏在」問題にすり替え、都道府県の権限強化、開業規制や管理者要件の拡大、地域別診療報酬といった制度改悪が進められようとしています。
このような政策は、患者窓口負担の増加と同じく、国民を医療から遠ざける方向に進んでいることは明白です。
高齢化が進むなかで、兵庫県内でも、地域に必要な医療が確保されない事例が増えつつあり、制度疲労は極限に達しています。
こうした状況に対し、当協会は、医科・歯科が一体となって政策提言を行い、現場の声を社会に届けることに取り組んできました。
行政や国会への要請、マスコミを通じた情報発信、他団体との連携など、さまざまな取り組みを粘り強く進めてきたことは、着実に社会を動かす力になっていると確信しています。
さて、昨年の兵庫県知事選では、当会理事の大澤芳清氏が立候補し、「現場から政治へ」という思いを体現する新たな挑戦をしていただきました。多くの会員の皆様が自発的に応援し、医師が現場に根差した知見と経験をもって、県民に政策を訴える姿勢を示すことができました。結果こそ伴いませんでしたが、この経験は、今後の政策提言や選挙対応においてかけがえのない財産となります。
これからも、各種選挙において、医療を守る政策を掲げる候補者や政党をしっかりと見極め、地域医療をよくする政策への転換を後押ししていく必要があります。
また、歯科分野においても、診療報酬や歯科医師数の抑制政策が進められていますが、10年後を見据えれば不足が明らかです。
さらに、口腔内の健康が誤嚥性肺炎や糖尿病、認知症の予防、さらには在宅医療の充実への寄与が明らかとなっている今、歯科医療の軽視は時代に逆行し、医療全体の後退につながりかねません。歯科技工士不足問題も深刻で、早急な対応が求められています。当然ながら、これらを支える歯科医療費の総枠拡大は待ったなしの状況です。
兵庫協会のように、医科と歯科が共に活動する体制は、今後の医療政策においてさらに重要な意味を持つと考えます。
これから、協会の活動はますます広がっていきます。
若手世代にとって、安心して働ける医療環境の整備は急務です。現在の制度では、いわゆる「やりがい搾取」が常態化しています。医師数の計画的増加と診療報酬の大幅な増加を同時に進めなければなりません。診療報酬の増額を第一に、労働時間規制への対応、専門医制度の改善、開業支援制度の整備など、次代を担う人材が希望を持てる仕組みづくりが求められており、それは私たち先達(せんだつ)の責務です。
協会の理念である「開業保険医の生活と権利を守る」「住民とともに地域医療を守る」を柱に、皆さまと共に持続可能な地域医療の未来を構築してまいります。今後とも皆さまのご支援をお願い申し上げ、冒頭のご挨拶とさせていただきます。
第57回総会挨拶 2025年6月
本日はご多用のなか、第57回総会にご出席いただき、ありがとうございます。
また、日頃より協会の活動にご支援・ご協力を賜り、感謝申し上げる。
昨今、協会活動を取り巻く環境は大きく変化し、医療制度も次々と新たな局面を迎えている。
この背景には、40年以上も前に登場した「医療費亡国論」に基づく「医療費抑制政策」がある。
「国民医療費の増高により、国がつぶれる」といった誤った前提が、今もなお制度設計の根幹に据えられ続けている現状は、極めて由々しきことである。「診療報酬制度」そのものも、現場の実態からかけ離れており、機能不全に陥っている。全国の病院の6割以上が赤字経営に陥っており、大学病院も例外ではない。内部留保は枯渇し、新たな投資どころか、医療機器の更新すらできない。兵庫県の直営10病院に至っては、すべてが2年連続赤字という深刻な状況にある。民間病院であれば倒産寸前である。このままでは、ある日突然、地域の基幹病院が無くなってしまう状況が現実のものとなりかねない。もちろん、こうした現状は、医療機関の過剰投資や放漫経営、現場の努力不足によるものではない。最大の理由は、制度全体に組み込まれた「医療費抑制政策」であり、現在の診療報酬では、大半の病院が医業を続けられないことが明らかになっただけである。診療所も例外ではない。利益率の最頻値がマイナス、という危機的状況で、倒産や廃業が地域医療に空白を生みかねない。少子高齢化、労働力不足を背景に、今後も賃金上昇とインフレ基調は続くと考えられるが、医療は公定価格のため、患者さんへの価格転嫁ができない。診療報酬の期中改定、補助金など緊急的な対応が必要である。
医師の需給に関しても、日本の医師数は、世界的にみて、依然として絶対的に不足しているにもかかわらず、この問題を「地域偏在」「診療科偏在」にすり替えている。現場の勤務医師は、その使命感、倫理観に基づき、長時間労働で地域医療を支えてきた。医師を増員しない「働き方改革」―つまり労働時間短縮は、供給側の縮小であり、患者さんに安全、安心で質の高い医療提供体制を維持することが難しくなりつつある。ところが現在、こうした現状を改善するどころか、現政権は一部の野党を引き込み、ベッド数削減、薬の保険外しなどによる医療費の大幅削減に合意している。
さらに、新たな地域医療計画、都道府県の権限強化、開業規制や管理者要件の厳格化、地域別診療報酬の導入といった制度改悪が進められようとしている。医療・福祉就業者数は900万人を超える、国内で3本の指に入る産業であり、経済波及効果、雇用創出効果も他業種に劣らず、経済成長の足をひっぱるお荷物ではない。それどころか地方では、重要な社会的インフラであり、なおかつ経済全体を支えている。一方で、患者さんの窓口負担も年々増加している。経済的理由による受診抑制は、公平を旨とする国民皆保険制度の理念に真っ向反するものである。「お金の心配をせずに医療を受ける」ことは、憲法に定められた「人権」そのものであり、それを保障するのは国の責務である。
歯科分野においても課題が山積している。歯科医師不足に先んじ、歯科技工士不足が深刻化している。このままでは10年後には、歯科医療提供体制の崩壊が明らかになるであろう。
これらを食い止めるためには、「保険適応範囲の拡大」「窓口負担の引き下げ」、そしてなによりも「歯科医療費の総枠拡大」が必須である。兵庫協会は、医科と歯科が一体となって活動する、全国でも貴重な体制であり、大きな強みとなっている。医科・歯科が力を合わせ、運動を活性化し情報発信を積極的に行っていく活動を一層強化していきたいと考える。
これまで、私たちは会内だけでなく、行政や国会への要請、マスコミを通じた広報活動、一般住民、他団体との連携といった取り組みを積み重ねてきた。これらの活動により、少しずつではあるが、社会に認められ、社会を動かす力となってきている。昨年の兵庫県知事選では、当会理事の大澤先生が立候補され、「現場から政治へ」を体現する新たな挑戦をしていただいた。多くの皆様から応援をいただき、医師が現場に根ざした知見と経験をもって、政策を訴える姿勢を示すことで、協会の社会的存在感を高めた。望む結果にはならなかったが、この経験は、今後の政策提言や選挙対応において、かけがえのない財産となった。
今後は、勤務医、開業医にかかわらず、次世代の医師・歯科医師が安心して医療に従事し、地域医療を守るための「環境整備」が不可欠である。これは私たち先達の責任でもある。診療報酬の増額、医師・歯科医師の増員、新専門医制度の改善、新たな地域医療構想や働き方改革への対応、開業支援、共済制度の提供など多方面から活動を進めていく所存である。
理事長としての10年間を振り返ると、医療・社会保障制度の改悪を完全に止めることはできなかったが、現場の声を集め、発信し、社会的な関心と議論を生み出す活動は、保険医協会にしかできない。協会の活動は今後ますます広がっていくが、私一人の力では到底実現できない。会員の皆さまの力が不可欠である。一人ひとりの声が集まれば、必ず大きな力となる。
本日の総会が、その一歩を力強く踏み出す機会となることを願い、冒頭のご挨拶とさせていただく。ご清聴ありがとう。
総会祝賀会での挨拶 2019年6月
本日は、ご多用のところ、このように多数の方々にご臨席を賜り、「設立50周年祝賀会」を執り行うことが出来、誠に光栄の至りです。
高いところからだが、こうして、皆様の、お一人お一人のお顔を拝見すると、長きにわたり様々なご支援を賜った事を思い、感謝の念を禁じえない。誠にありがとうございます。
とりわけ、本日ご臨席の、医学・医療を指導していただいている病院の先生方、平素よりご懇意にさせていただき、たびたびご無理申し上げている国会議員の先生方、ご指導・ご鞭撻を頂いている「全国保険医団体連合会」並びに各都道府県の保険医協会・医会の先生方、私どもの活動にご理解ご協力をいただいている医療関係団体の皆様、共済事業を通じてご協力いただいている生命保険会社・損害保険会社の皆様、親しくお付き合いさせていただいている友好団体の皆様、お取引いただいている業者様、並びに協会顧問の弁護士、税理士の先生方に厚くお礼申し上げます。
ご来賓の方々のお名前をすべてご紹介することは叶わないが、ご参加いただいた皆様のお力添えとご支援のおかげ様をもち、本日50周年という喜びの節目を迎えることができ、あらためて皆様のご厚情に感謝申し上げます。
これからは、国民健康保険の都道府県単位化なども実行され、医療社会保障分野における都道府県の権限と役割が一層強くなっていきます。半ば強制的な機能別病床数のコントロールや医師の地理的偏在解消、県独自の診療報酬点数設定なども危惧されます。
さて、ここで協会の半世紀を、スライドを使って簡単にご紹介します。まず、初代理事長・桐島正義先生。協会は、1963年十数人の有志により結成された「兵庫保険医クラブ」を前身としています。保険医クラブ6年間の活動を経て1969年、764人の会員からなる「兵庫県保険医協会」が設立されました。「開業保険医の経営と生活、権利を守る」「国民医療の充実と向上をはかる」という二つの大きな目的を掲げてスタートしました。
初代歯科部会長・田村武夫先生。兵庫県保険医協会は、医師法・歯科医師法の第一条に定められているように、「公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する」ために、早くより医科・歯科一体となって活動しています。
合志至誠・第二代理事長。1995年、阪神・淡路大震災が発生し、協会は被災患者支援と民間医療機関への公的支援拡充を求めました。「復興県民会議」を中心に、日本医師会の協力も得ながら、医療機関向けの助成制度を認めさせ、その後の災害対応の基礎となっています。
池尻重義・第三代理事長。協会は受診抑制を伴い、格差医療を招く「患者窓口負担増加」へは一貫して反対しています。協会は、財政優先の社会保障費抑制に対して、医療政策研究を重ね、会内外に発信し、国民とともに、皆保険制度を守り続けてきました。
第4代理事長・朝井栄先生。2000年には介護保険制度が創設されました。協会は医療だけにとどまらず、介護保険の充実をはじめ、命、健康を脅かす、いわゆる「健康の社会的決定要因」の改善にも力を注いできました。
前理事長・池内春樹先生。この当時、産科・小児科・救急を中心に「医療崩壊」がもたらされたのは、記憶に新しいかと思います。協会は、社会保障全般、あるいは健康に関する問題意識を共有する各団体とも協働して活動してきました。
協会設立当時の私。中学入学直後、人生で3カ月間だけ丸刈りを強制され、この頃より「非従順な知性」が芽生えていました。体重は50年でおよそ2倍になりました。まだまだ力不足ですが、歴代理事長に一歩でも近づけるよう、努力したいと思います。本日この日を、新たな50年へのスタートとしたいと思います。
当協会の50年間の活動と業績は、歴代理事長をはじめ、協会役員延べ259人を中心に、すべての会員、そして事務局員の協力と努力の結果です。この場を借りて、ご逝去された方、並びに先人たちのご尽力に感謝し、今日の慶事を共に喜びたいと思います。
お陰様を持ち、共に活動する会員数は、設立以来、毎年増加を続け、現時点では過去最高となる7520人となりました。医科歯科一体の協会としては全国2番目の規模となりました。
私ども協会の目的は「国民医療の向上と充実をはかる」ことです。これは立場を超えた国民の強い願いであり、私たち医師・歯科医師の責務であり、追い求め続け、達成すべき目標です。
兵庫協会は、今日のこの日を、先達たちが築き上げてきたこの道をより太く、明るく、はっきりと示す第一歩としたいと思います。
設立当初の情熱を忘れず、慢心することなく、医科・歯科一体となって、困難と問題に立ち向かい、理想と目標に向かって進むことを、会員一同改めて決意しています。皆様方におかれては、これまでと変わらない、ご指導とご鞭撻、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、ご臨席賜りました皆様のご健勝とご多幸を祈念し、私のご挨拶とさせていただきます。有難うございました。
就任挨拶 2015年6月

兵庫県保険医協会
理事長 西山 裕康
この度、兵庫県保険医協会の理事長に就任いたしました西山裕康です。
平素は協会の活動にご理解、ご協力賜わりまして誠に有難うございます。私たち兵庫県保険医協会は、現在医師・歯科医師合わせて7200人を超える組織です。「患者住民とともに地域医療の充実・向上をめざす事」を大きな柱とし、命と健康を守る社会の実現に向け活動しています。
さて、最近の医療・社会保障改革を見ますと、小泉改革に始まる「公的医療にブレーキ」に加えて、安倍内閣における「医療の営利産業化にアクセル」という新自由主義的政策により、多くの医療関係者が巻込まれ、一部は押し切られあるいは取り込まれ、その結果、健康弱者を始めとする社会的弱者にその「しわ寄せ」が及んでおります。
日本の国民皆保険制度には、先人たちが作り上げてきた「いつでも、どこでも、だれでも」という理想があります。この理想を守り続ける事により、国民が最適な医療を享受できるという、世界に誇れる日本の医療制度を再確認し、その体制を堅持しさらに充実させるべきです。
「いつでも、どこでも、だれでも」に反する「今だけ、ここだけ、自分だけ」を決して良しとせず、「能力に応じて負担、必要に応じて給付、結果として所得再分配を伴う」という社会保障の原則を当然とし、基本的人権としての医療・社会保障を守り続ける活動に邁進したいと思っております。
兵庫県保険医協会の大きな柱は「患者・住民とともに地域医療の充実・向上をめざす」事です。そのためには皆様方のお力も必要ですので、今後とも協会の活動にご理解とご協力、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
以上、簡単ですが理事長就任の挨拶とさせていただきます。